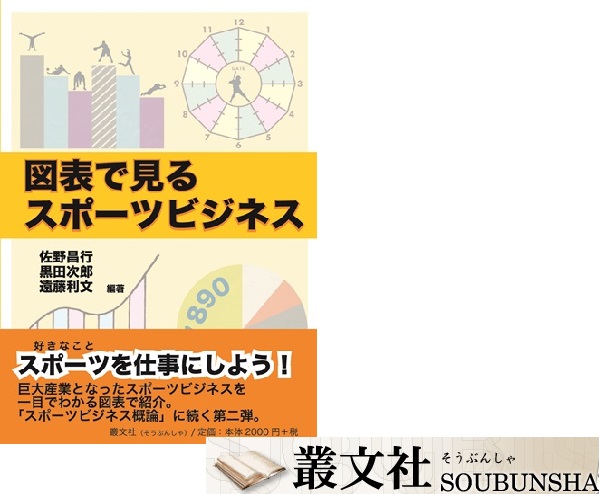株式会社シンキーはBIO tech 2014にて、自転・公転ミキサー「あわとり練太郎」を出展。
自転と公転の遠心力で、攪拌と脱泡の同時処理を行えるミキサーを紹介。
[BIO tech 2014] 自転・公転ミキサー「あわとり練太郎」 – 株式会社シンキー
[BIO tech 2014] 薬用保冷庫「MediFridge FMS-304GU」 – 福島工業株式会社
福島工業株式会社はBIO tech 2014にて、薬用保冷庫「MediFridge FMS-304GU」を出展。
従来にない観音開きタイプで、省エネ性能と高精度な温度制御を実現した薬用保冷庫を紹介。
[BIO tech 2014] 細胞代謝アナライザー「XFe Series」 – プライムテック株式会社
プライムテック株式会社はBIO tech 2014にて、細胞代謝アナライザー「XFe Series」を出展。
細胞のエネルギー代謝経路を無侵襲・経時的に計測できる細胞代謝アナライザーを紹介。
[BIO tech 2014] チップ自動交換式自動固相抽出システム – 岩下エンジニアリング株式会社
岩下エンジニアリング株式会社はBIO tech 2014にて、チップ自動交換式自動固相抽出システムを出展。
汎用性のある自動分注ロボットMODEL-100に高精度分注ポンプと固相抽出システムを組み合わせた装置を紹介。
[BIO tech 2014] 小型魚類集合水槽システム「LABREED」 – 株式会社イワキ
株式会社イワキはBIO tech 2014にて、小型魚類集合水槽システム「LABREED」を出展。
1台で小型魚類など数多くの個体の生体管理が容易に行えるシステムを紹介。
カジノ法制化見据え東京で国際会議
5月14日から16日の3日間、コンラッド東京で「ジャパンゲーミングコングレス(JGC)」が開催される。
JGCは統合型リゾート(IR)とカジノ関連の会議で、海外のカジノ事業者や国内外の有識者が東京に集結する。カジノ法制化の動きなどについて最新事情や市場性について語られる。主催のクラリオンイベンツ社によると、主な議題は下記の通り。
・どのような規制アプローチが期待される結果をもたらすのか?
・カジノが将来的に観光業界やエンターテイメント業界に及ぼす影響
・IR開発への投資の実態とアジアのゲーミング関連消費者
・日本で営業するゲーム機製造業者に対する認定・ライセンス手順の理解
・市場の潜在力 – 高い期待を実現するロードマップはあるか?
ほか
主な登壇者は、大阪商業大学アミューズメント産業研究所所長の美原融氏、ラスベガスサンズの最高執行責任者マイケル・レヴィン氏、ゴールドマン・サックス証券の杉山賢氏など。最終日には、展示会とMICE誌にIR関連の記事を連載している国際カジノ研究所の木曽崇所長も登壇し、マネーロンダリング防止のコンプライアンスなどについて議論する。
【お知らせ】「見本市展示会通信」デジタル版販売をスタート~『デジタル新聞ダイレクトby honto』から~
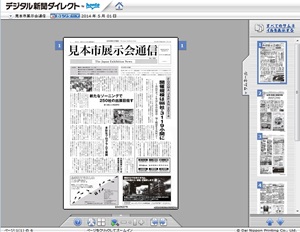
「見本市展示会通信」(発行:(株)ピーオーピー、毎月1日・15日/月2回)は、紙面と同じレイアウトのデジタル版を閲覧できるサービスでの販売を、5月8日から開始しました。
販売は、大日本印刷(株)(DNP)が『デジタル新聞ダイレクトby honto』としてスタートした、パソコンや携帯端末で専門紙・業界紙の新聞が閲覧できる有料の会員制デジタル新聞販売サービスを通じて行ないます。『デジタル新聞ダイレクトby honto』では、第一弾として「食品・飲料」「建設・住宅」など、「見本市展示会通信」を含め17紙(12社)が販売されます。
DNPは、サービス開始の背景として「専門紙・業界紙は、特定の分野・業界の製品やサービス、市況などの非常に詳細な情報が掲載されており、関連する企業や団体、大学や専門学校などで重視され、多く購読されている。専門紙・業界紙には、顧客への提案資料の作成、研究開発、業界動向の把握などに有益な情報が多数掲載されていることから、購読先で回覧されることが多い反面、紙媒体での発行が主体であるため、デジタル化による企業内の複数人で同時閲覧や社外への持ち出しなどが可能となるサービスが求められていた」とニーズを分析。ハイブリッド型総合書店「honto(ホント)」で培った電子書籍販売のノウハウを活かして、新聞のデジタル版を提供する『デジタル新聞ダイレクトby honto』を開発し、今回5月からサービスを開始しています。
現在、プレオープンサービスとして、5月8日から6月1日までに会員登録をした対象者に限り、この期間中は無料で閲覧することができます。
【『デジタル新聞ダイレクトby honto』サービス開始第一弾の専門紙・業界紙】
◇食品・飲料分野
・日本食料新聞、日食外食レストラン新聞、百菜元気新聞(日本食料新聞社)
・日本外食新聞、外食日報(外食産業新聞社)
・冷食タイムス、水産タイムス(水産タイムズ社)
・醸造報知(醸造報知新聞社)
◇建設・住宅分野
・建設通信新聞(日刊建設通信新聞社)
・週刊住宅(週刊住宅新聞社)
・週刊ビル経営(ビル経営研究所)
・リフォーム産業新聞、工務店新聞(リフォーム産業新聞社)
・建設技術新聞(建設技術新聞社)
・インテリアビジネスニュース(インテリア情報企画)
◇その他併読できるデジタル新聞
・文化通信(文化通信社)
・見本市展示会通信(ピーオーピー)
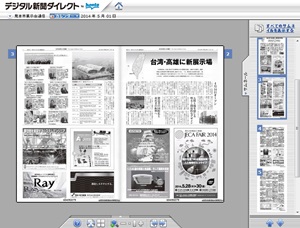
【「見本市展示会通信」デジタル版】
新聞社名:株式会社ピーオーピー
発行日:月2回発行(毎月1日・15日)
体裁:タブロイド
購読料:1部価格:500円 (消費税:40円) 合計:540円
月極め定期購読価格:850円 (消費税:68円) 合計:918円
【書籍紹介】イベント・旅行産業にも言及、「図表で見るスポーツビジネス」
叢文社は、4月7日、「図表で見るスポーツビジネス」を発行した。編著者は、佐野昌行氏(日本体育大学 体育学部 社会体育学科 助教)、黒田次郎氏(近畿大学 産業理工学部 経営ビジネス学科 准教授)、遠藤利文氏(スポーツデータバンク 代表取締役)の3氏。
「図表で見るスポーツビジネス」は、巨大産業となったスポーツビジネスを一目でわかる図表で紹介したもので、同社から出版されたスポーツビジネスの現状を解説した「スポーツビジネス概論」(黒田次郎・遠藤利文編著)の第二弾となる。
“スポーツ産業にはどのような領域があるのか”、“産業規模はどの程度か”、“スポーツ産業におけるビジネスの仕組みは”といった疑問に3氏のほか、スポーツ科学の分野の研究者とスポーツ産業で活躍する実務家ら多彩な執筆陣が答える内容となっており、6部22章で構成。
第一部でスポーツ産業の全体像や歴史、政策との関係を概観したうえで、第二部から六部ではそれぞれスポーツ指導、スポーツ空間・用品、スポーツ医療・コンディショニング、プロスポーツ、スポーツイベント・旅行の各産業の現状や動向について解説している。特徴的なのは、いずれの章でも、多くの図や表を用い、視覚的に理解できるよう構成されているほか、コラムなども挿入されており、親しみやすい内容となっている。
なお、『第六部スポーツイベント・旅行の産業-第19章スポーツイベント産業-』では、スポーツイベントを運営するセレスポでサステナブルイベント研究所所長を務める越川延明氏、地域経営コンサルタントの丹野実氏も執筆し、経済波及効果やマネジメント面について言及。イベント・MICE業界の関係者にとっても参考となりそうだ。
大学でスポーツマネジメント・スポーツ経営・スポーツビジネス等について学ぶ学生向けの本書ではあるが、スポーツにかかわる仕事をはじめるビジネスマン・自治体担当者にとっても、スポーツ産業の全体像をつかむ一冊となっている。
本体¥2,000+消費税。詳細については、叢文社のwebサイトまで。
http://www.soubunsha.co.jp/sofind.cgi?isbn=7947-0724
愛 台湾 ひぐち日記【その2.台湾MICEに乾杯編】

4月10日から15日までの6日間、MICE関連のメディアを集めた台湾MICEツアーにピーオーピーは参加しました。
先週のメルマガでは、台湾到着初日、Wi-Fi事情と、TWTC(台北世界貿易センター)やTICC(国際会議センター)など、国際展示場・国際会議場周辺エリアのナイトライフ環境視察のもようをお伝えしましたが、2日目からは、いよいよ中国・英国・日本と、3国4メディアの記者たちとメディアツアーがスタート。台湾MICEを支えるさまざまな立場の関係者からお話を聞くため、まずは台北市内の4か所をめぐりました。
■Kuei Jung Exhibition Co.,LTD.
 最初にお話を伺ったのは、展示会主催・運営会社Kuei Jung Exhibitionの総経理(社長)の周孝慶さんです。BtoC展を中心に年間約40本の展示会を主催。台湾の展示会主催会社のなかでも、台北・台中・高雄の3か所に支店をもつ唯一のPEOです。旅行や玩具、電化製品など多岐にわたる分野の展示会を立ち上げてきました。同社の代表的な主催展は、漫画とアニメの展示会。昨年8月の展示会「2013 The 14th Comic Exhibition」では、これまでで最多となる58万人の動員を6日間で達成しています。
最初にお話を伺ったのは、展示会主催・運営会社Kuei Jung Exhibitionの総経理(社長)の周孝慶さんです。BtoC展を中心に年間約40本の展示会を主催。台湾の展示会主催会社のなかでも、台北・台中・高雄の3か所に支店をもつ唯一のPEOです。旅行や玩具、電化製品など多岐にわたる分野の展示会を立ち上げてきました。同社の代表的な主催展は、漫画とアニメの展示会。昨年8月の展示会「2013 The 14th Comic Exhibition」では、これまでで最多となる58万人の動員を6日間で達成しています。
1989年の会社設立当初は、外資系主催会社の代理業務から開始、BtoBの展示会を扱っていましたが、20年ほど前に自ら主催業務をするようになり、BtoCの展示会主催へとシフトしたといいます。

「BtoC専門のPEO(Professional Exhibition Organizer)となったのは、産業構造の変化が理由として挙げられる。消費財の展示会に関して言えば、台湾では以前より国際展示会の必要性が減少してきている。それは、輸出よりも国内需要を拡大する傾向にあるから。日本や中国でもBtoCに強い市場の産業展示会は将来性あるのではないか」と周さんは話します。
消費動向を捉え、昨年はシルバー向けの展示会、健康産業の展示会を新規に立ち上げている。また、台湾の3か所で展示会を主催・運営する上では、地元の
商習慣にローカライズすることが重要で、同じ台湾でも北と南でも違うもの。地元に密着した企業と共同で進めていくことが展示会成功の秘訣だといいます。
■TECA(Taiwan Exhibition and Convention Association)
 次に訪れたのは、台湾の展示会および会議関連の企業・団体約140社が会員となっているTECA。副理事長であるKitty Wongさんに対応いただきました。TECAは2008年6月18日に設立された団体で、展示コンベンション産業の促進・経済的発展を目的に、TECAメンバーの関係を調和させ、共通の利益を促進するなど、政策や法律の実施面で政府のMICE推進を支援している団体です。会員間の交流だけでなく、国際交流の促進も大きな活動の一つで、国際団体AFECA(Asian Federation of Exhibition & Convention Association)にも加盟しています。
次に訪れたのは、台湾の展示会および会議関連の企業・団体約140社が会員となっているTECA。副理事長であるKitty Wongさんに対応いただきました。TECAは2008年6月18日に設立された団体で、展示コンベンション産業の促進・経済的発展を目的に、TECAメンバーの関係を調和させ、共通の利益を促進するなど、政策や法律の実施面で政府のMICE推進を支援している団体です。会員間の交流だけでなく、国際交流の促進も大きな活動の一つで、国際団体AFECA(Asian Federation of Exhibition & Convention Association)にも加盟しています。
ちなみに、Kittyさんご本人はK&A International社、Expo Union Corporation社の社長も務めており、国際的に幅広いネットワークをもち、つい先週も日本のPCO会社の社長とミーティングをしてきたばかりだと言います。(弊社媒体では以前K&A International社の代表としてインタビュー記事を掲載しました。)

「TECAメンバーにはPEO、PCO、メディア、設計・デザイン、旅行会社、運輸、宿泊、人材、会場運営などさまざま。お互いにできないことや能力的にむずかしいことなどをTECAとして請け負い、補完しあうことで実現しています。たとえば、海外での展示会運営を検討していた会員会社が経験豊富な他の会員会社とコラボレーションして実施するなど、TECAはそのつなぎ役となっているのです」とKittyさんは話す。そのため、会員間の情報共有にも力を入れており、fax、e-mail、webサイトとeメールニュースで連携を取り合っているという。
■経済日報
 3件目は、台湾の経済紙メディアで最大手である経済日報へ。35万部を発行する経済日報では、展示会主催事業も30年来続けており、さきほど訪れたTECAのメンバーでもあります。BtoBの専門展示会を年間約10件開催しており、もっとも規模が大きい自動化工業展は、台北・台中・高雄と3か所で展開。そのほか、建材、クルマなどの展示会も手がけています。また、台湾では民間で初の会場建設・運営を台中で行なっている。
3件目は、台湾の経済紙メディアで最大手である経済日報へ。35万部を発行する経済日報では、展示会主催事業も30年来続けており、さきほど訪れたTECAのメンバーでもあります。BtoBの専門展示会を年間約10件開催しており、もっとも規模が大きい自動化工業展は、台北・台中・高雄と3か所で展開。そのほか、建材、クルマなどの展示会も手がけています。また、台湾では民間で初の会場建設・運営を台中で行なっている。

総経理(社長)兼董事長(会長)の周祖誠さんは、「メディアにとって、専門展を手がけるメリットは、第一に全体の売上の12~13%のシェアがあること、第二に新聞の読者数増につながること」と話す。展示会は現在国内市場がメインとなっているが、今後は国際展示会としての拡大を目指し、UFI(世界見本市連盟)などとのコンタクトも頻繁に行なっているという。また、各国の展示会サービスについて研究開発を進めており、今年からアプリ開発にも着手、4月23日からの「高雄自動化工業展」から開始、出展メーカーの情報や会場マップ、ブース紹介などの機能を備え、来場者向けに提供していく。
そのほか、北京や香港で企業の経営者を参加対象とした経済フォーラム事業も進めており、メディア、イベント、会場と連携しながら、台湾のメイン産業の情報プラットフォームとしての役割を果たしている。
■TAITRA(台湾貿易センター)
 メディアツアー1日目のさいごには、TAITRA副秘書官であり、台湾MICEの国際マーケティングプロモーション“MEET TAIWAN”の推進役である葉明水マネージングディレクターに最新動向のプレゼンテーションを受けました。場所は、TAITRA本部のある世界貿易ビルの眺望のよい一室。
メディアツアー1日目のさいごには、TAITRA副秘書官であり、台湾MICEの国際マーケティングプロモーション“MEET TAIWAN”の推進役である葉明水マネージングディレクターに最新動向のプレゼンテーションを受けました。場所は、TAITRA本部のある世界貿易ビルの眺望のよい一室。
MEET TAIWANは、2010年度から台湾経済部国際貿易局がMICE産業の推進業務を手がけ、2億元の資金を割り当て「台湾におけるコンベンション拡大計画(=MEET TAIWAN)」プロジェクトとして発足させているもの。
葉さんは「MEET TAIWANの推進によって、グループ団体客数は年間2400万人となりました。IT、電子部品の製造拠点でもある台湾では技術者向け会議も多く、
台北はアジア第4位の国際会議都市となっています。展示会分野でも、国内向けの展示会だけでなく国際展示会開催に向けても注力しており、今年は高雄展覧館がオープンするほか、2017年には台北のTWTC南港を拡大し、合計で10万平米・6500ブースを展開できる大型展示会場へと発展させます」と今後の計画を明かした。

その後、同じ場所でメディア一行は、MEET TIWANのメンバらーとuniplanで高雄展覧館を担当している陳乗鴻さん、TECAのKittyさんも合流し、夕食とともに、台湾式乾杯をしました。

台湾式ではグラスを少し高くかかげ「乾杯」と杯を空中で合わし、くいっと一気に飲み干します。そして、グラスの底を皆にみせて「杯を乾かしましたよ」ということを示します。グラスをテーブルに置くと、すかさず次のお酒を注がれるという格好。ワイングラスにほんの少し(日本の1/5程度)しか注がれないのは、この「乾杯」用のジャストな量だというやさしさに気づきました。発音も「カンペイ」と日本語と似た親近感も手伝って、円卓のみなさんと目が合うとこの「乾杯」を繰り返すという文化交流で1日目を締めくくったのでした。
4か所をめぐりましたが、中国の展示会専門メディアからは幾度となく台中間の連携についての質問がありました。MICE産業はサービス業にカテゴリーされる分野であり、その分野ではまだ貿易締結がなされていないことや、情報共有の必要性があることなど、まずは国家・政府間の支援が待たれるとのこと。優遇措置などの政策的対応が先決のようです。
1日目、MICEの「E」のソフト面についてBtoCの、BtoBの各主催者からの話には、20年、30年と台湾産業の成長とともに展示会を育ててきたという自負とともに、常にいまのニーズを捉え最先端のトレンドを発信・提供していくという意欲を感じました。その実現のために、TECAのメンバーシップやMICE推進に向け国策として進めるMEET TAIWANが推進力となっています。立場は違えど、お会いした4者それぞれの皆さんがもつ使命感が台湾MICEを大きく前進させているという印象を受けました。(ピーオーピー樋口陽子)
【愛 台湾 ひぐち日記バックナンバー】
イメージングの新機軸と産業175年の歴史を融合 ~フォトキナ2014
ケルンメッセは9月16日から21日の6日間、ドイツのケルンメッセ会場で写真・イメージング分野の見本市「フォトキナ ワールド・オブ・イメージング2014」を開催する。
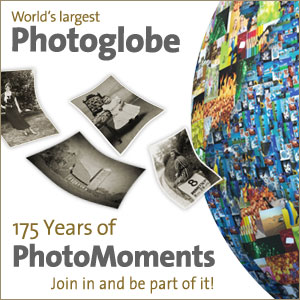 同展は2年に1回開催され、世界各国の主要メーカーが新製品発表を行なうなど、最新技術やトレンドの情報発信の場となっている。前回開催には73か国6000人以上のジャーナリストを含む、166か国から18万5000人が来場。業界関係者のうち42%が海外からの参加と世界中の注目を集める。
同展は2年に1回開催され、世界各国の主要メーカーが新製品発表を行なうなど、最新技術やトレンドの情報発信の場となっている。前回開催には73か国6000人以上のジャーナリストを含む、166か国から18万5000人が来場。業界関係者のうち42%が海外からの参加と世界中の注目を集める。
今回の開催については、すでに展示面積の80%が申込み済みとなっており、最終的には40か国から1000社の出展が見込まれている。
会場は、カメラ・レンズなどの機器の「キャプチャー・ユア・ワールド」、照明やフラッシュ、三脚の「ライトアップ・ユア・ワールド」、保存や接続、転送に関する「シェア・ユア・ワールド」、入力や編集、加工の「クリエイト・ユア・ワールド」、仕上げ、印刷、表現などの「ショウ・ユア・ワールド」など5つのゾーンに分けて展示される。
注目されるテーマはアクションカメラ、動画撮影、インターネット接続の3点。製品の展示紹介だけでなく、業界の最新動向の講義、撮影技術のレクチャー、ビジネス成功に向けたセミナー、プロ・アマ向けのワークショップなどさまざまなプログラムが企画されている。
 1839年に銀板写真が発明されて175周年。その変遷をたどる記念展示も実施。歴史と新機軸が同居するイベントとなりそうだ。
1839年に銀板写真が発明されて175周年。その変遷をたどる記念展示も実施。歴史と新機軸が同居するイベントとなりそうだ。
出展申込みや問合せはケルンメッセ(03-5793-7770)まで。