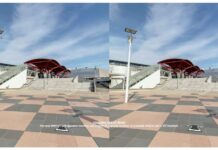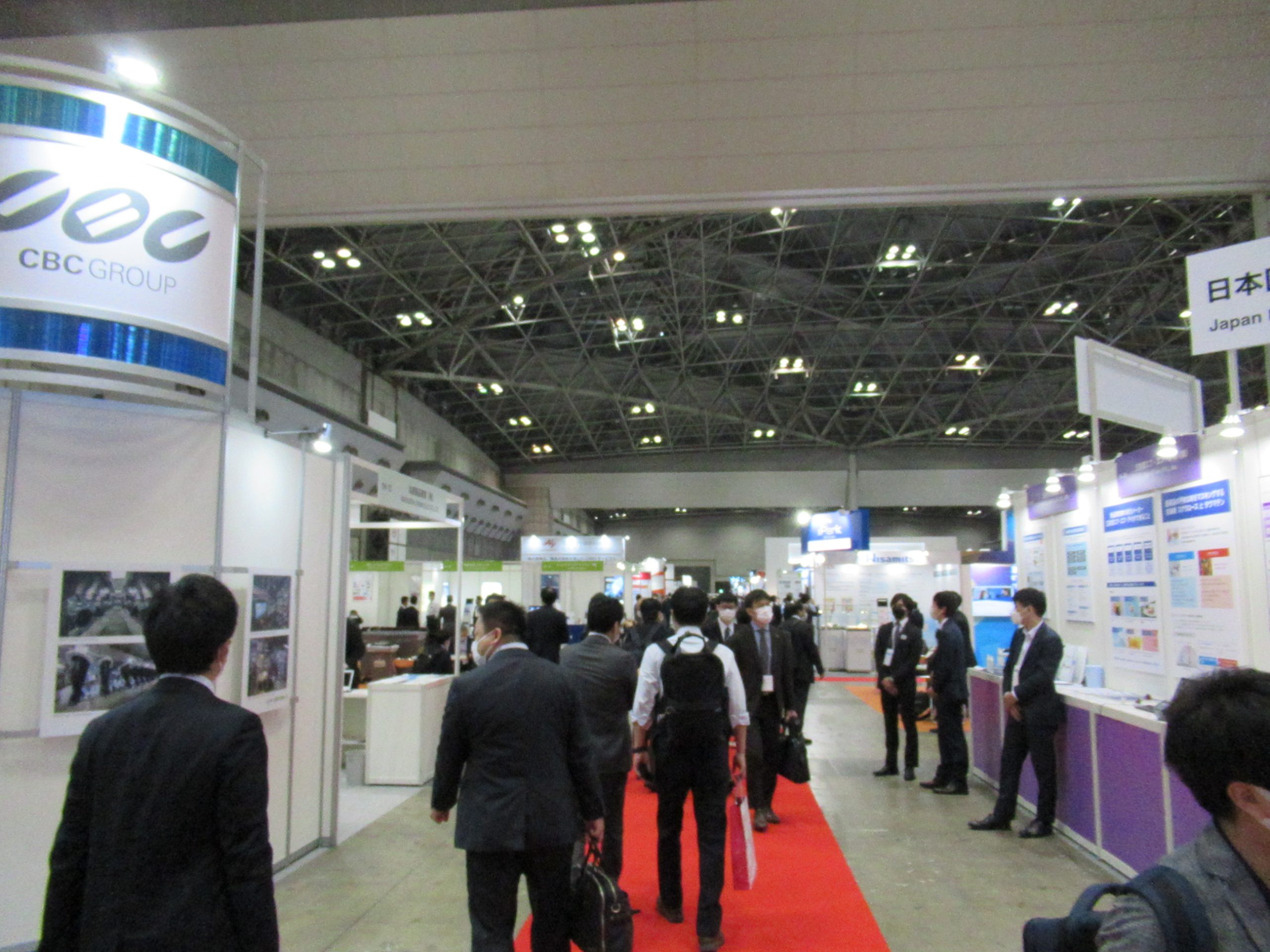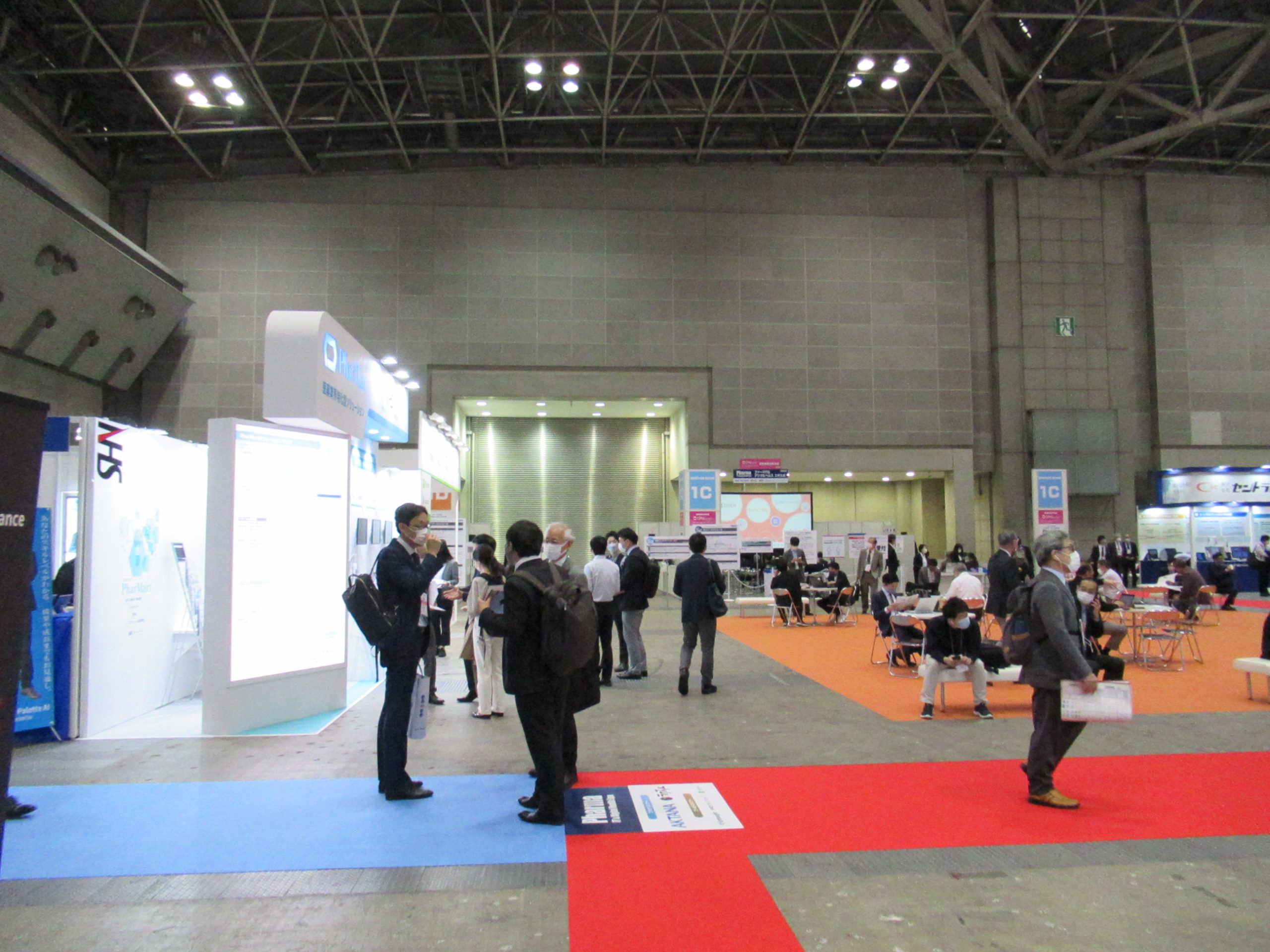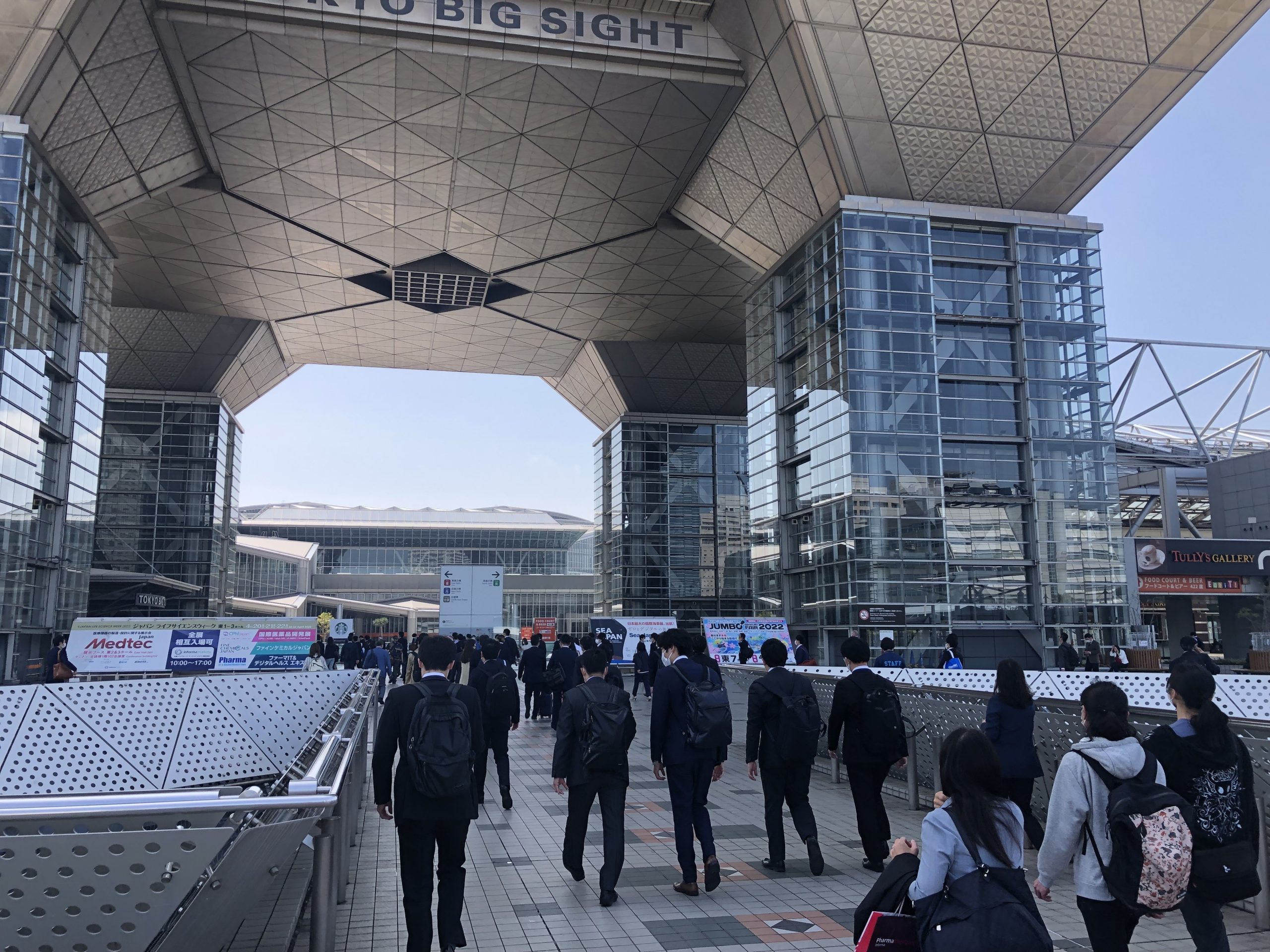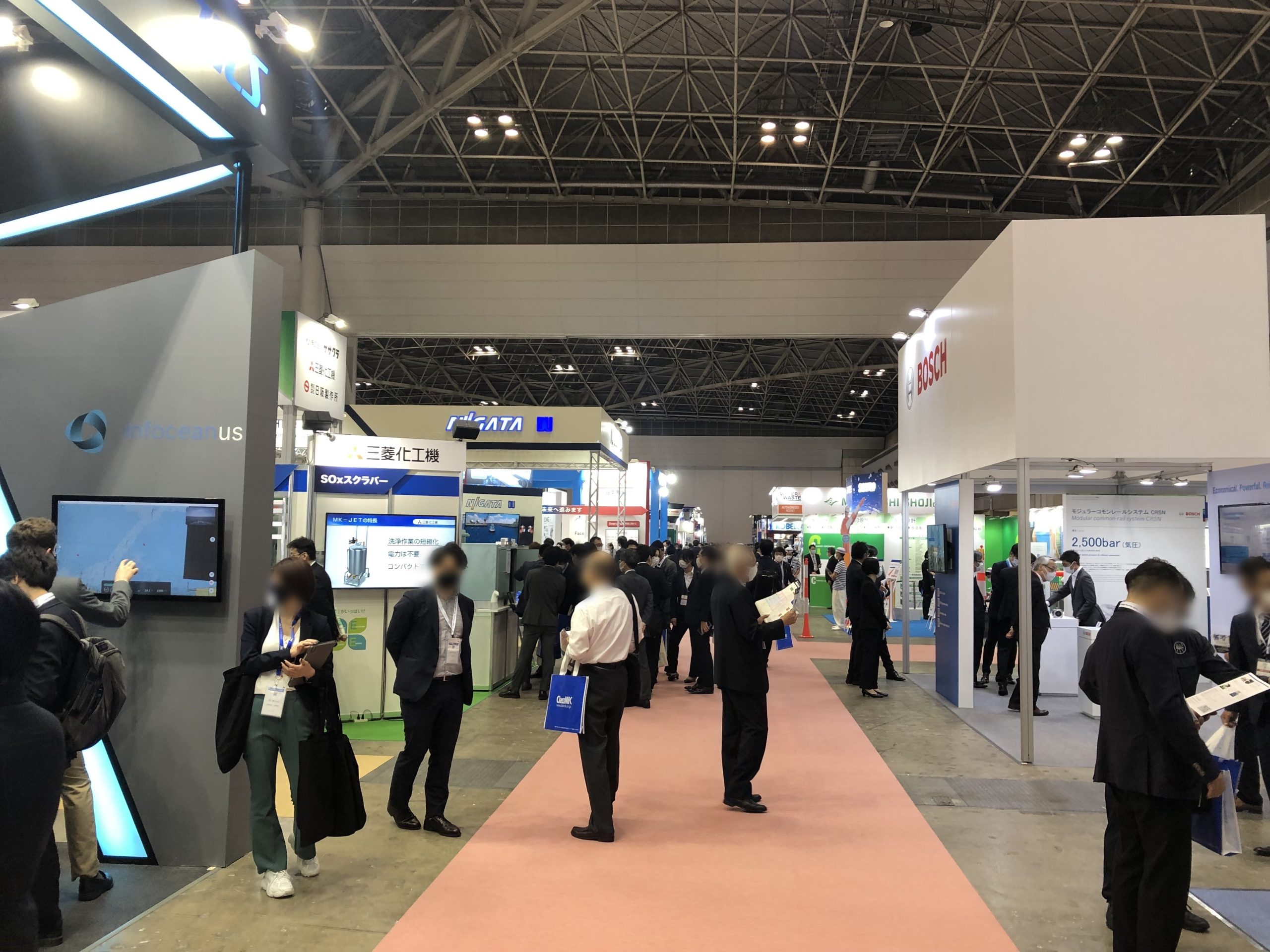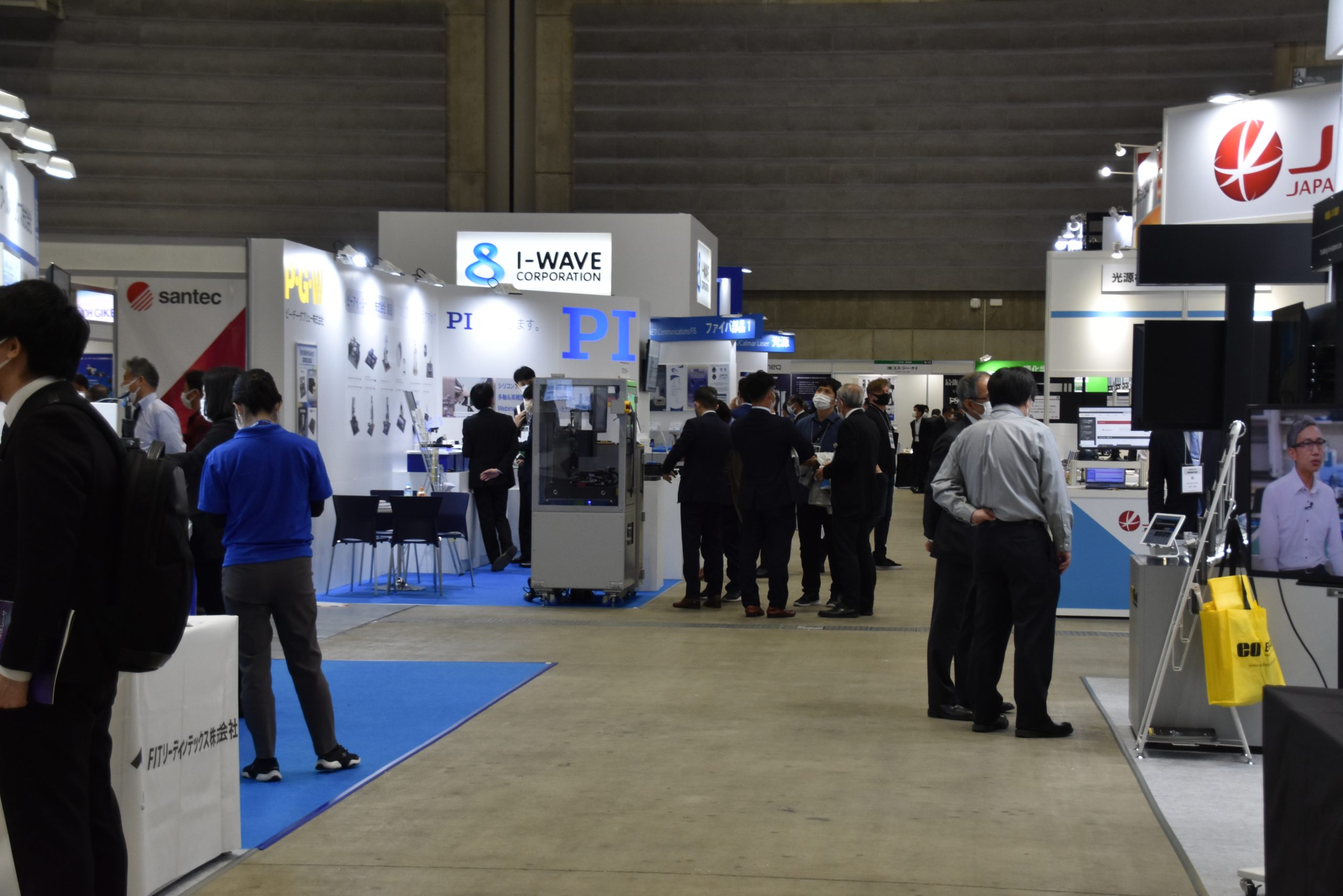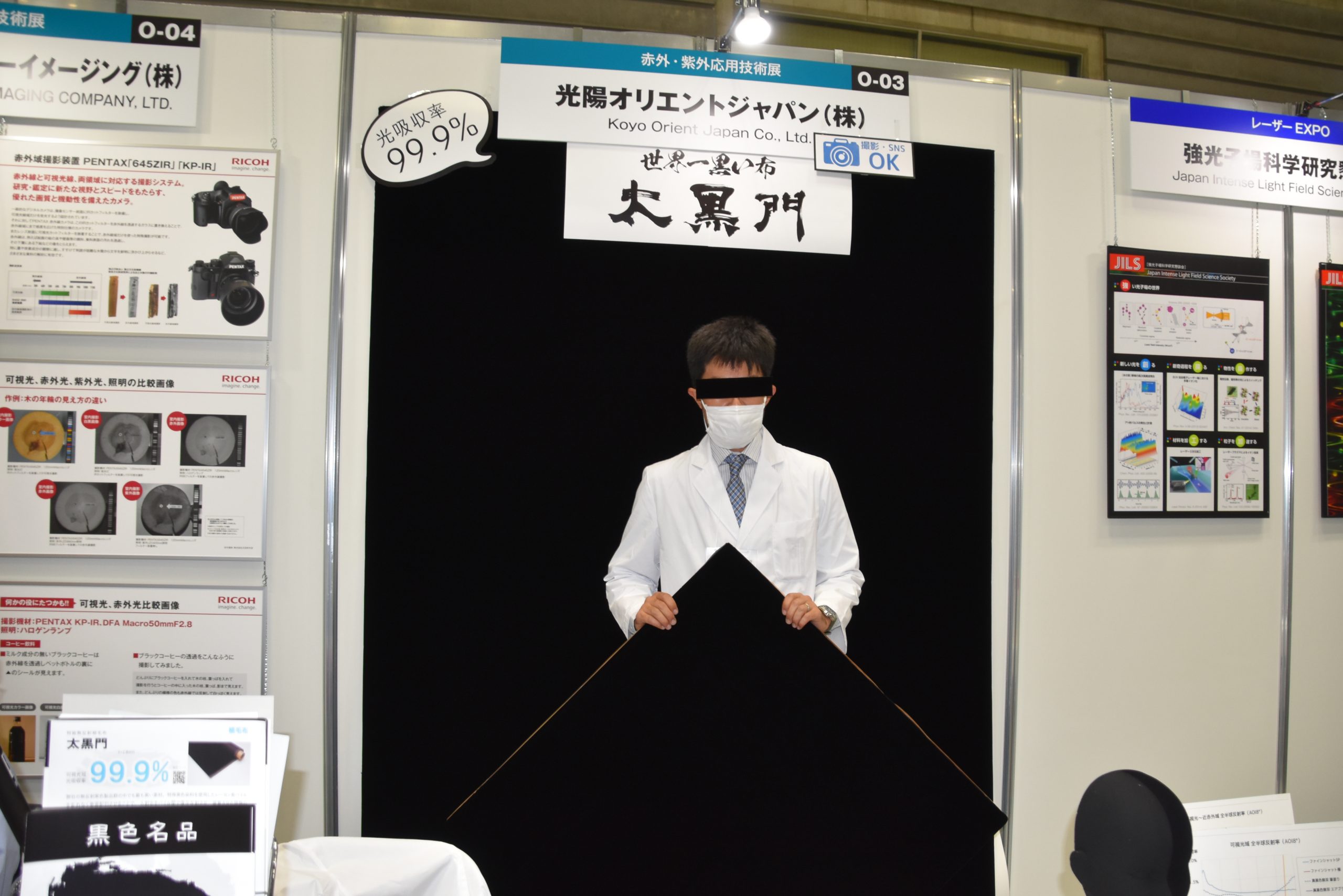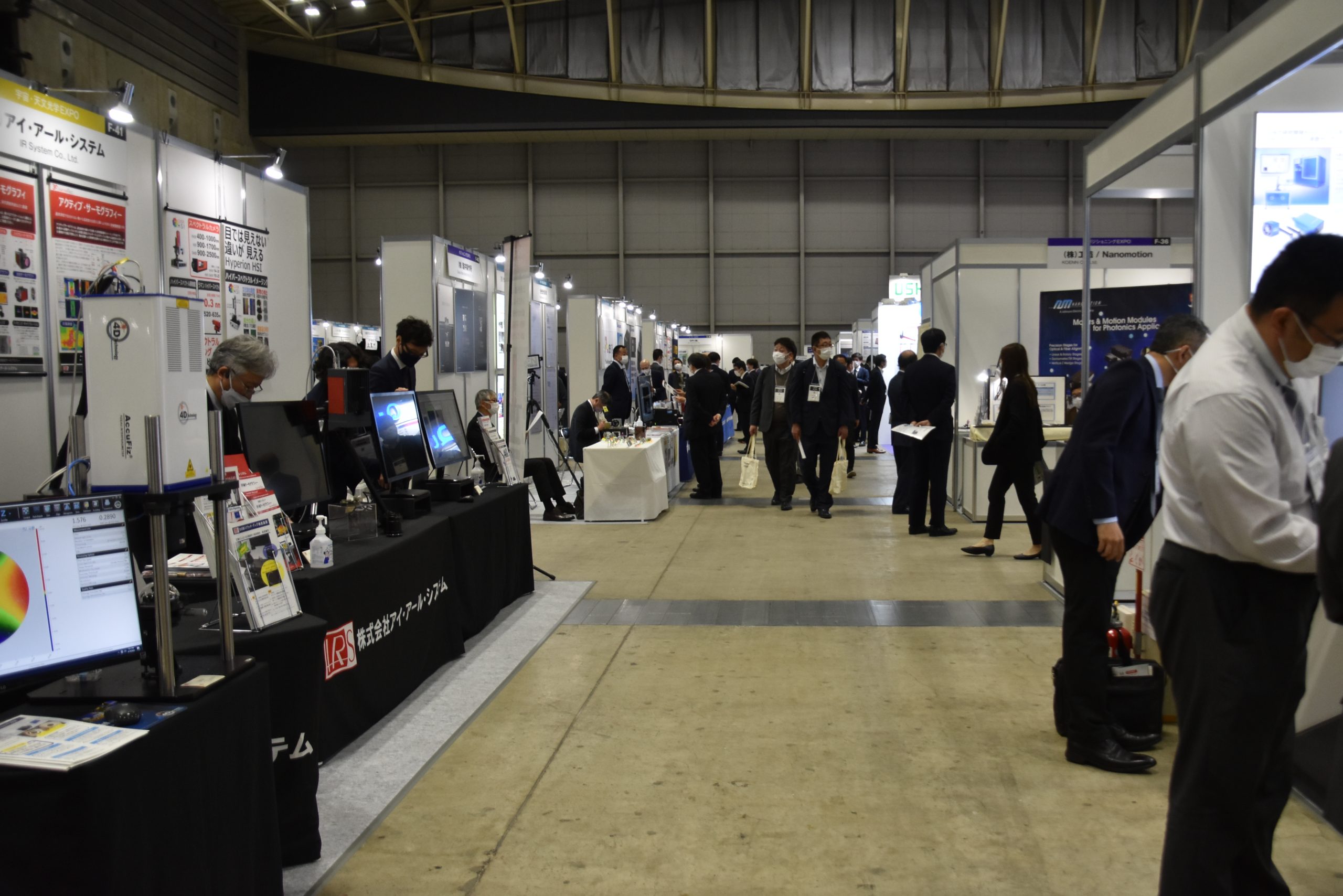※2023年1月30日現在、以下の内容は変更されています。
最新の政府のイベント制限・施設利用制限の詳細はこちらのページをご覧ください
1.イベントの開催制限
(1)特定都道府県(緊急事態宣言措置下)
ア. イベントの開催制限の目安等
(ア)イベント開催の目安を以下のとおりとする。特定都道府県は、以下を目安とする規模要件等を設定し、それに基づいたイベント(開催される施設等の種類を問わない。以下同様とする。)の開催をイベント主催者等に対して、法第24条第9項に基づき要請すること。
①感染防止安全計画(安全計画の概要については、令和4年2月10日付け事務連絡を参照)を策定し、都道府県による確認を受けた場合
人数上限10,000人かつ収容率の上限を100%とする。
さらに、別途定める対象者に対する全員検査を実施した場合には、人数上限を収容定員までとすることを可能とする。
なお、対象者全員検査におけるワクチン接種歴又は検査結果の陰性を確認する対象者は、定められた人数上限(緊急事態措置区域においては10,000人)を超える範囲の入場者とする。
②それ以外の場合
人数上限5,000人かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)とする。
※「大声」の具体例は下記の(4)留意事項を参照
なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より1年間保管すること。
①及び②のいずれの場合についても、特定都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、COCOA 等の活用等について、イベント主催者等に周知すること。
イ.営業時間短縮等の要請
原則、要請を行うことを求めないが、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、開催時間を制限する要請を行うことも可能とする。
ウ.チケット販売の取扱い等
(ア)緊急事態措置の公示が行われた日から、最大3日間の周知期間終了後までにチケット販売が開始された場合(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)には、周知期間終了までに販売されたものに限り、上記ア.及びイ.は適用せず、販売したチケットを自らキャンセルする必要はないものとイベント主催者等に周知すること。
(イ)上記周知期間後に販売開始されるものは、上記ア.及びイ.を満たすこと。
エ.公示された緊急事態措置を実施すべき期間終了後に開催予定イベントの取扱い等
公示された緊急事態措置を実施すべき期間終了後に開催予定のイベントのチケットを販売する場合は、措置期間の延長が行われる可能性があることを踏まえて、慎重を期すこと。
(2)まん延防止等重点措置区域である都道府県
ア.イベントの開催制限の目安等
(ア)イベント開催の目安を以下のとおりとする。都道府県は、以下を目安とする規模要件等を設定し、それに基づいたイベントの開催をイベント主催者等に対して、法第24条第9項に基づき要請すること。
①安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合
人数上限は収容定員までかつ収容率の上限を100%とすることを基本とする
②それ以外の場合
人数上限5,000人かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)とする。
なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より1年間保管すること。
①及び②のいずれの場合についても、都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、COCOA 等の活用等について、イベント主催者等に周知すること。
イ.営業時間短縮等の要請
原則、要請を行うことを求めないが、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、開催時間を制限する要請を行うことも可能とする。
ウ.チケット販売の取扱い等
(ア)まん延防止等重点措置の公示が行われた日から、最大3日間の周知期間終了後までにチケット販売が開始された場合(優先販売など、名前の如何に関わらず、何らかの形で販売が開始されているもの)には、周知期間終了までに販売されたものに限り、上記ア.及びイ.は適用せず、各都道府県が定めた周知期間までに販売したチケットを自らキャンセルする必要はないものとイベント主催者等に周知すること。
(イ)上記周知期間後に販売開始されるものは、上記ア.及びイ.を満たすこと。
(3)その他の都道府県
ア.イベントの開催制限の目安等
(ア)イベント開催の目安を以下のとおりとする。都道府県は、以下を目安とする規模要件等を設定し、それに基づいたイベントの開催をイベント主催者等に対して、法第24条第9項に基づき要請すること。
①安全計画を策定し、都道府県による確認を受けた場合
人数上限は収容定員までかつ、収容率の上限を100%とする。
②それ以外の場合
人数上限5,000人又は収容定員の50%いずれか大きい方かつ収容率の上限を50%(大声あり)又は100%(大声なし)とする。
なお、この場合、都道府県が定める様式に基づく感染防止策等を記載したチェックリストをイベント主催者等が作成・HP等で公表する。イベント主催者等は、当該チェックリストをイベント終了日より1年間保管すること。
①及び②のいずれの場合についても、都道府県は、イベント等の開催に当たっては、その規模に関わらず、「三つの密」が発生しない席の配置や「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、イベントの開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係るイベント主催者等による行動管理等、基本的な感染防止策が講じられるよう、イベント主催者等に対して強く働きかけるとともに、参加者名簿を作成して連絡先等を把握しておくことや、COCOA 等の活用等について、イベント主催者等に周知すること。
(4)留意事項
ア.感染拡大防止に必要な取組の継続等
収容定員が設定されていない場合、大声ありのイベントは、十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)を確保し、大声なしのイベントは人と人とが触れ合わない程度の間隔を確保すること。
なお、大声ありのイベントについて、十分な人と人との間隔(できるだけ2m、最低1m)の維持が困難な場合は、開催について慎重に判断すること。
飲食を伴う又は飲食が可能であるイベントについては、感染者が飲食した場合の周辺への感染リスクを高める可能性があることから、引き続き、飲食専用エリア以外(例:観客席等)においては自粛を求めることとする。ただし、発声が無いことを前提に、飲食時以外のマスク着用担保や、マスクを外す時間を短くするため飲食時間を短縮する等の対策ができる環境においてはこの限りではない。
イ.法第24条第9項に基づく要請等を行う場合の留意事項について
要請等については、個々の事業者や施設管理者等を対象として行うことは差し支えないが、当該要請等は行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第1項第6号の行政指導に該当すると考えられることから、同法及び各都道府県の行政手続条例に則り、当該要請の趣旨及び内容並びに責任者を相手方に明確に示す必要があることに留意し、徹底すること。
また、個々の事業者や施設管理者等に対して要請等を行う判断の考え方や基準について合理的説明が可能であり、公正性の観点からも説明ができるものになっているかといった観点からも検討を行うこと。
ウ.収容率の目安判断に当たっての留意事項等について
収容率の目安判断に当たり、「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。
<大声の具体例>
観客間の大声・長時間の会話
スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱
※得点時の一時的な歓声等は必ずしも当たらない。
エ.問題が確認されたイベント主催者等への対応等について
省略
オ.各種イベント・行事の開催判断に当たっての留意事項等
関係各府省庁及び各都道府県においては、各種イベント・行事の開催判断に当たって、イベント開催時に必要な感染防止対策の徹底や開催制限の目安を踏まえた開催規模・時期の検討等に加え、例えば、部活動等における成果を発揮する場として全国大会等の開催は重要であること等、個々の行事が有する事情に鑑み、開催のあり方を個別具体に検討する必要がある。
各種イベント・行事の開催判断に際して、各部局間の調整等を適切に実施し、感染防止策の徹底を図るとともに、各行事・イベントの趣旨を踏まえつつ、開催のあり方を適切に判断すること。
ただし、感染が急速に拡大し、医療提供体制の逼迫が見込まれる場合等においては、対象者全員検査等を適用せず、強い行動制限を要請することとする点に留意し、5,000人を超えるイベントのチケット販売については、慎重を期すこと。
カ.その他留意事項等について
「イベント」には特定都道府県や重点措置区域である都道府県全域において、遊園地やテーマパーク等を含むことに留意すること。
2.施設の使用制限等
(1)特定都道府県
特定都道府県は、法施行令第11条第1項に規定する施設を対象に、以下の要請又は働きかけを実施すること。
なお、特定都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。
ア.飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(第45条第2項等)
(ア)飲食店(第14号)
特定都道府県は、法第45条第2項等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む。酒類及びカラオケ設備の提供(利用者による酒類の店内持込みを含む。)を取り止める場合を除く。)に対して休業要請を行うとともに、上記以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)に対して、営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うこと。
ただし、都道府県知事の判断により、第三者認証制度の適用店舗(以下「認証店」という。)において21時までの営業(酒類提供も可能)もできることとするほか、認証店において、対象者全員検査を実施した場合には、収容率の上限を50%としつつ、カラオケ設備を提供できることとする。
その際、休業等の要請に応じている施設と応じていない施設との公平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令等の手続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に行うこと。公表する際には、令和3年7月8日付け事務連絡「特措法に基づく命令違反に係る過料決定店舗公表の留意事項等について(周知)」のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗については、その旨をコロナ室に報告すること。
特定都道府県は、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする。
以上の要請に当たっては、特定都道府県は、関係機関とも連携し、休業要請、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための対策・体制の更なる強化を行い、原則として全ての飲食店等に対して見回り・実地の働きかけを行うとともに、当該取組について適切に情報発信を行うものとする。
令和4年1月7日付け事務連絡「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その3)」等も踏まえて、特定都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めること。
(イ)遊興施設(第11号)のうち、飲食業の許可を受けている飲食店及び飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)
特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食業の許可を受けている飲食店及び飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)に対し、前記2.(1)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。ただし、飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)におけるカラオケ設備の提供については、認証店であることを要件としないが、業種別ガイドラインを遵守するよう要請を行うこと。
(ウ)結婚式場等
特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食業の許可を受けている結婚式場等に対し、前記2.(1)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。
なお、披露宴等をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。
イ.集客施設への要請等(法第24条第9項等)
(ア)特定都道府県は、基本的対処方針三(5)1)等に基づき、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、法第45条第2項等に基づき、人数管理、人数制限、誘導等の「入場者の整理等」「入場者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等、法施行令第12条に規定される各措置について事業者に対して要請を行うこと。
また、上記の要請に際しては、以下のような例示を参考に、人が密集すること等を防ぐため、「入場者の整理等」を行うよう事業者に要請するとともに、入場整理等の実施状況についてホームページ等を通じて広く周知するよう働きかけること。
その際には、人数管理・人数制限等について、例えば以下のような方法があることに留意すること。なお、ここでいう「入場者の整理等」とは、入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置と、施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置の双方を含むものである。
施設全体での措置
出入口にセンサー、サーモカメラ等を設置し、入場者・滞留者を計測し人数管理を行う
出入口の数の制限、入構制限、駐車場の収容上限の一時的削減等により人数制限を行う
売場別の措置
入口を限定し係員が入場人数を記録、入場整理券・時間帯別販売整理券の配布、買い物かごの稼働数把握、事前のWeb登録等により人数管理を行う
一定以上の入場ができないよう人数制限を行う
アプリで混雑状況を配信できる体制を構築する
(イ)関係各府省庁においては、関係団体への周知等、上記施設における要請の遵守徹底、感染防止対策の徹底等に必要な措置を講じること。
(2)重点措置区域である都道府県
法施行令第11条第1項に規定する施設を対象に、都道府県知事の判断により、以下の要請又は働きかけを行うこと。
なお、各都道府県が各種要請を行う場合にはエッセンシャルワーカーの事業環境を踏まえた配慮を行うなど、適正な法運用を図ること。
ア.飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(法第31条の6第1項等)
各知事が定める期間及び区域において、以下のとおり取り扱うこと。
(ア)飲食店(第14号)
都道府県は、措置区域において、法第31条の6第1項等に基づき、認証店以外の飲食店(宅配・テイクアウトを除く。)に対する営業時間の短縮(20時までとする。)の要請を行うとともに、酒類の提供を行わないよう要請するものとする。また、認証店に対しては、営業時間の短縮(21時までとすることを基本とする。)の要請を行うこととする。
この場合において、地域の感染状況等を踏まえ、都道府県知事の判断により、酒類の提供を行わないよう要請することも可能とする。
(また、都道府県知事の判断によっては、営業時間の短縮の要請を行わないことも可能とする。)
その際、営業時間の短縮等の要請に応じている施設と応じていない施設との公平性を保つため、要請に応じない場合には、速やかに、命令等の手続きを開始し、命令を行った店舗名については公表を積極的に行うこと。公表する際には、令和3年7月8日付け事務連絡「特措法に基づく命令違反に係る過料決定店舗公表の留意事項等について(周知)」のとおり取り扱うこと。また、命令等を行い公表する店舗については、その旨を当室に報告すること。
都道府県は、措置区域において、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする。
(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)
以上の要請に当たっては、都道府県は、関係機関とも連携し、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための対策・体制の更なる強化を行い、原則として措置区域内の全ての飲食店等に対して見回り・実地の働きかけを行うとともに、当該取組について適切に情報発信を行うものとする。
令和4年1月7日付け事務連絡「飲食店における感染防止対策を徹底するための第三者認証制度の導入について(改定その3)」等も踏まえて、都道府県は、実効性ある第三者認証制度の普及と認証店の拡大に努めること。
(イ)遊興施設(第11号)のうち、飲食業の許可を受けている飲食店及び飲食を主として業としていない店舗(カラオケ店等)前記2.(2)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。
(ウ)結婚式場等
基本的対処方針三(5)2)等に基づき、飲食業の許可を受けている結婚式場等に対し、前記2.(2)ア.(ア)と同様の要請を行うこと。
なお、披露宴等をホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)で行う場合も同様の条件を求めるものとする。
イ. 上記ア.以外の法施行令第11条第1項に規定する施設(特に大規模な集客施設)(法第24条第9項等)
都道府県は、基本的対処方針三(5)2)等に基づき、地域の感染状況等に応じて、都道府県知事の判断により、措置区域において、法第31条の6第1項等に基づき、「入場をする者の整理等」「入場をする者に対するマスクの着用の周知」「感染防止措置を実施しない者の入場の禁止」「会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等)」等、法施行令第5条の5に規定される各措置について事業者に対して要請を行うこと。
要請に際しては、法第31条の6第1項に基づく要請は、業態に属する事業を行う者に対し行うものであることに留意すること。
なお、ここでいう「入場者の整理等」とは、入場者が密集しないよう整理・誘導する等の措置と、施設の入場者の人数管理・人数制限等の措置の双方を含むものであることに留意すること。
(3)その他の都道府県
ア. 飲食店及び飲食に関連する施設への要請等(法第24条第9項)
都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、法第24条第9項に基づき、飲食店に対する営業時間の短縮の要請を行うこと。この場合において認証店以外の店舗については20時までとし、認証店については要請を行わないことを基本とする。
都道府県は、感染拡大の傾向が見られる場合には、法第24条第9項に基づき、飲食店等及び飲食店等の利用者に対し、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避けるよう要請するものとし、認証店における対象者全員検査を実施した会食については、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食も可能とする。
(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)
上記の要請に当たっては、都道府県は、営業時間の短縮や第三者認証制度等の遵守を徹底するための見回り・実地の働きかけを進めるものとする。
3.外出・移動
(1) 特定都道府県
特定都道府県は、法第45条第1項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛について協力の要請を行うこと。
特に、感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用を厳に控えることについて、住民に徹底すること。また、不要不急の帰省や旅行等都道府県間の移動は、極力控えるように促すこと。この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする。
特定都道府県は、法第45条第1項に基づき、路上・公園等における集団での飲酒など、感染リスクが高い行動に対して、必要な注意喚起や自粛の要請等を行うとともに、実地の呼びかけ等を強化するものとする。
(2)重点措置である都道府県
都道府県は、措置区域において、法第31条の6第2項に基づき、営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないよう、住民に対して要請等を行うこと。
都道府県は、措置区域において、法第24条第9項に基づき、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出・移動の自粛及び感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること等について、住民に対して協力の要請を行うこと。また、不要不急の都道府県間の移動、特に緊急事態措置区域との往来は、極力控えるように促すこと。
この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする。
(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)
(3)その他の都道府県
都道府県は、帰省や旅行等、都道府県をまたぐ移動は、「三つの密」回避を含め基本的な感染防止策を徹底するよう促すこと。また、緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は、極力控えるように促すものとし、この場合において、対象者全員検査を受けた者は、その対象としないことを基本とする。
(都道府県知事の判断により、ワクチン・検査パッケージ制度を適用し、上記の取扱いを行うことを可能とする。)
都道府県は、業種別ガイドライン等を遵守している施設等の利用を促すこと。
都道府県は、感染拡大の兆候や施設等におけるクラスターの発生があった場合、政府と連携して、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出の自粛に関して速やかに住民に対して必要な協力の要請等を行うこと。