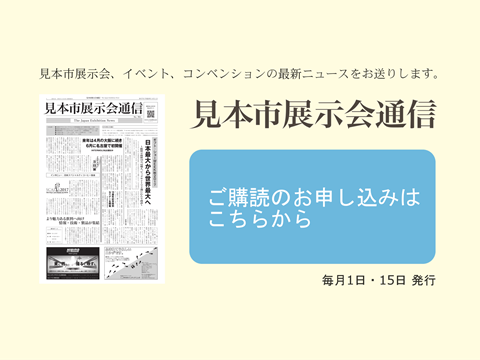Tel:025-243-6827
FAX:025-241-0768
担当:野口 貴史【第1営業部】
noguchi@shinsen.biz
-
見本市
展示会 -
会議
学会 -
内覧会
発表会 -
パーティ
シンポジウム -
スポーツ
-
音楽
-
販売促進
-
文化
食
会社概要
- 事業内容
-
見本市・展示会、式典・大会、学術会議、その他各種イベントのデザイン・設計
製作、施工、運営業務までの一元管理、事務局代行 - イベント実績
-
●ものづくり ワールド [東京]・ [大阪]・[名古屋]
●JIMTOF
●スーパーマーケット・トレードショー
●フードメッセinにいがた
●にいがた酒の陣
●医学系学術会議
●企業プライベートショー
●海外テストマーケティング・商談会
ほか - 主なサポートエリア
- 東北 関東 中部
| 本社TEL | 025-243-6827 |
|---|---|
| 設立 | 1986年1月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役会長 佐野 由香利 |
| 従業員 | 33名 |
| 年間売上高 | ─ |
| 事業所 | ●東京営業所(東京都江東区) ●上越営業所(新潟県上越市) ●台湾連絡事務所 グループ会社:㈱シンセンホールディングス、㈱シンセンリフォーム、㈱井浦建設、SHINSEN VIETNAM Co., Ltd. |
| 加入団体 | 日本展示会協会・新潟県ディスプレイ協同組合、東京ディスプレイ協同組合・新潟県広告美術業協同組合、日本イベント業務管理者協会・新潟県建築士会、新潟経済同友会・新潟商工会議所、新潟観光コンベンション協会 ほか |







-218x150.jpg)