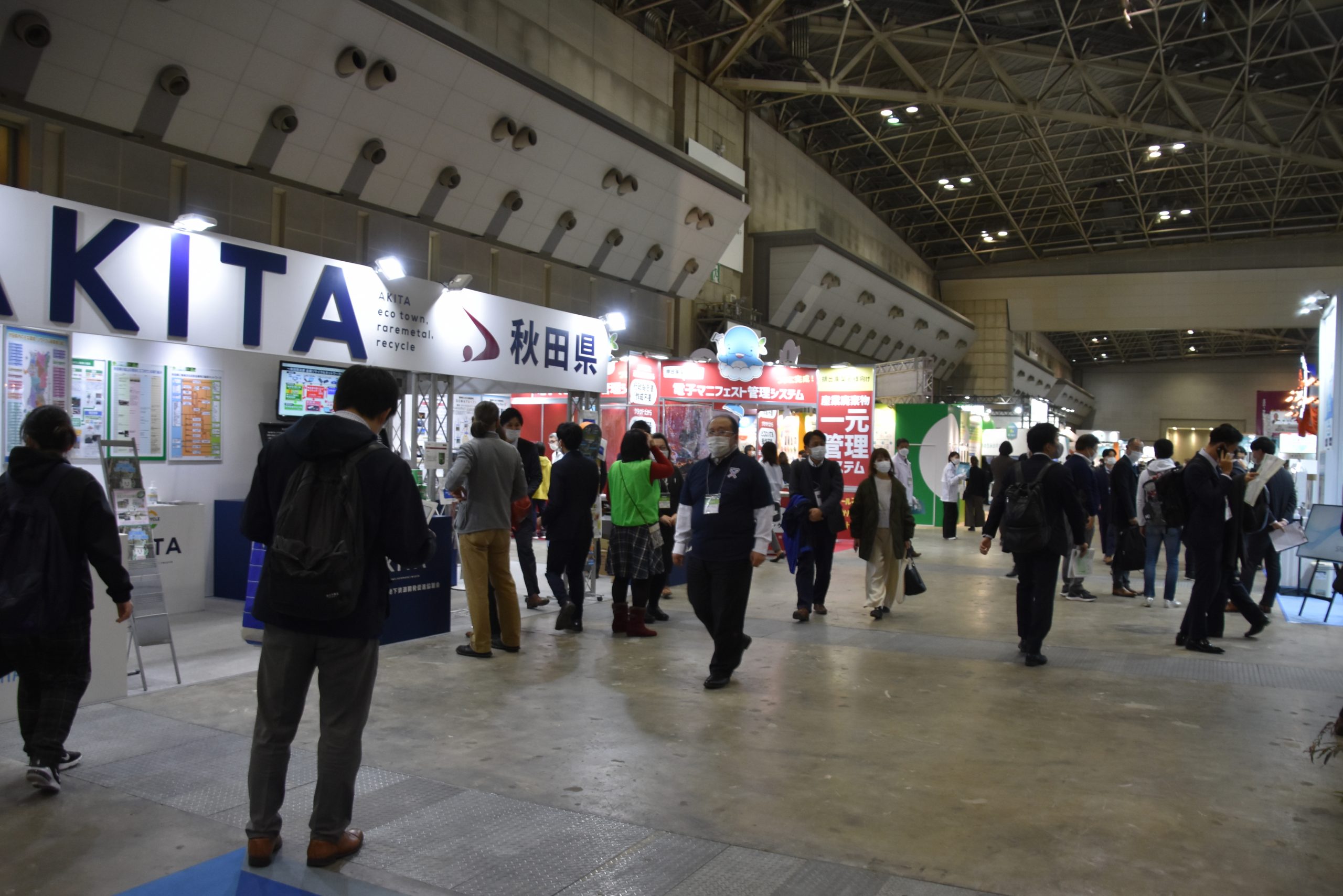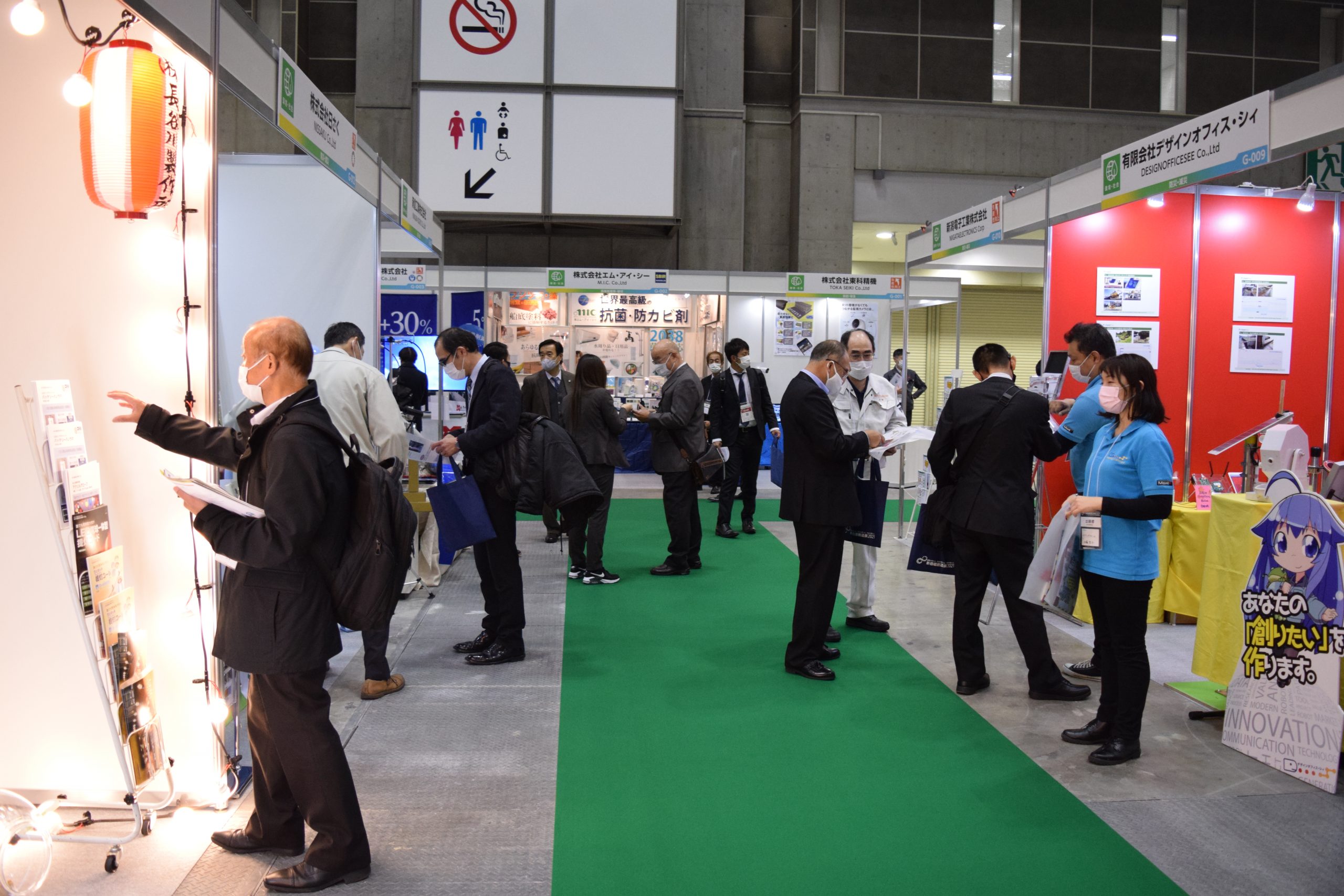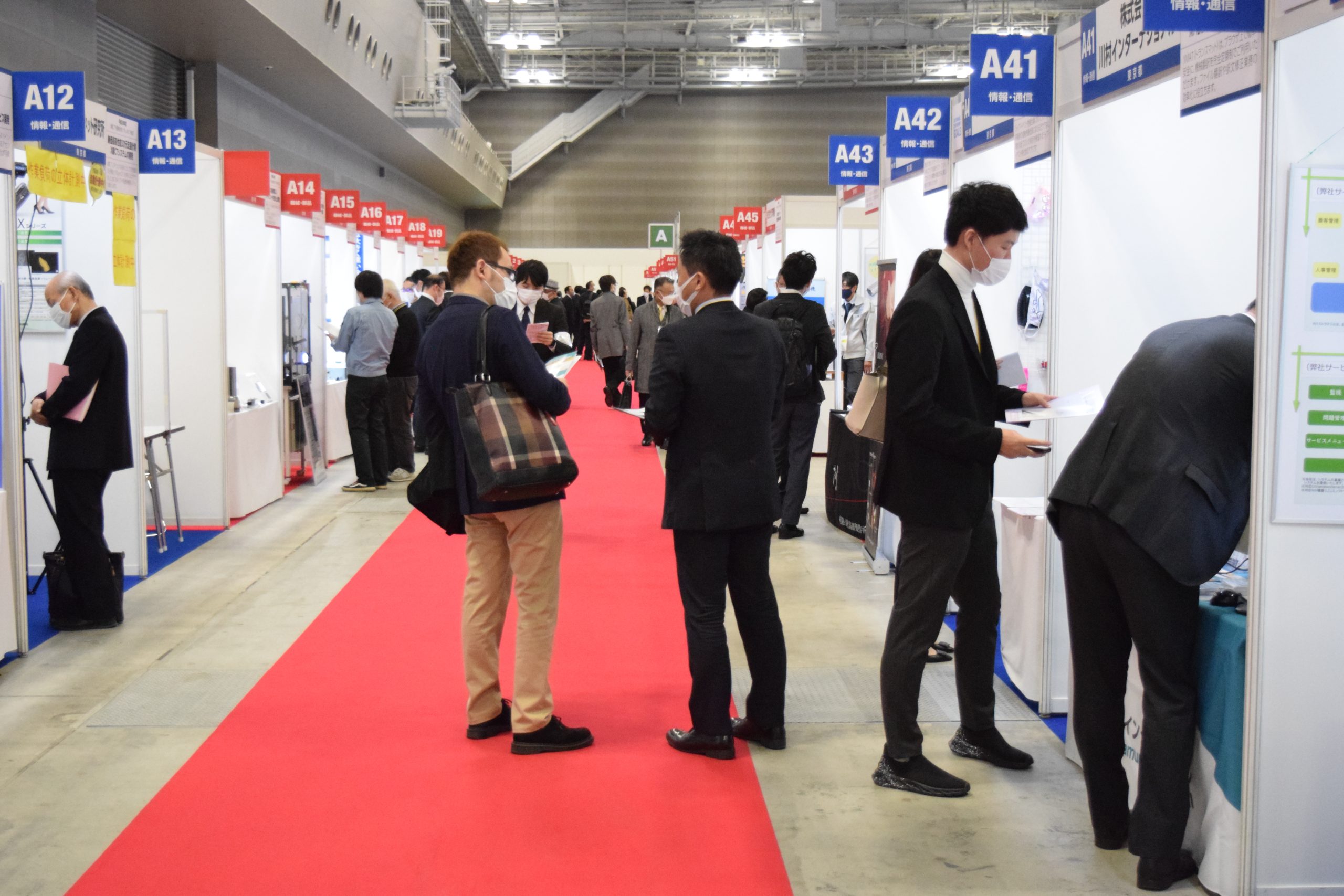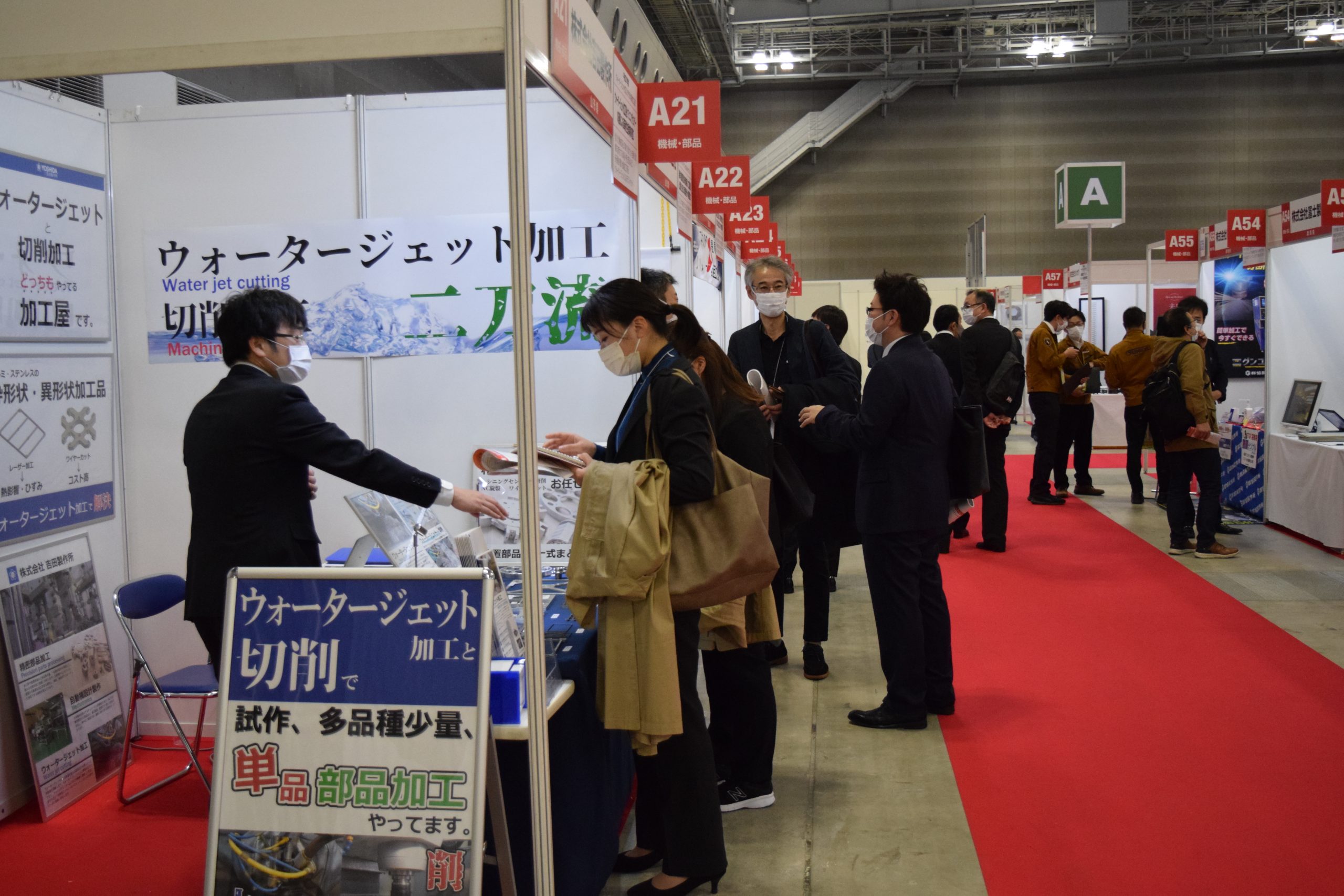日産自動車は12月2日から12月27日まで、本社ギャラリー(神奈川・横浜市)で「Nissan Futures」を開催している。日産の電動化への挑戦の歴史を振り返りながら、現在の技術やコンセプトカーなどを体感できるイベントで、今回はオンラインツアーも実施している。グローバルブランドエクスペリエンス部・青山真理子氏とグローバルマーケティングストラテジー本部・栗原一郎氏にイベントの見どころを聞いた。
誰にでも「電動化」を分かりやすく
今回のイベントは、日産自動車が重要視する“電動化”をテーマに、一般層にも分かりやすく理解でき、楽しめるよう構成されている。青山氏は「お客様とコミュニケーションをはかり、情報を伝え続けることは非常に大切。長期ビジョン『Nissan Ambition 2030』を発表したタイミングで、われわれができるコミュニケーションの場として本社ギャラリーでイベントを開催するに至った。ここまで大きなイベントの開催は初めて」という。「電動化を推進していく中で、社会への貢献はもちろん、何よりお客様に楽しんでもらいたいと考えている。イベントを通じて“どちらも選ぶ”日産の姿勢を感じていただきたい(青山氏)」

リアル、バーチャル上でコンセプトカーを体感
過去・現在・未来の3つのゾーンに分かれている会場には、それぞれ電気自動車や最新技術が展示され、日産の電動化の歴史や思いに触れることができる。公道で実際に「オーラ」や「ノート」などの試乗体験ができるほか、今回、発表された4台のコンセプトカーのうちの1台である「NISSAN CHILL-OUT」は実寸大モデルが展示されている。そのほかの3台は展示はないものの、バーチャルステージ上で視聴や記念撮影ができる体験型コンテンツ(Concept Car Virtual Stage)が用意されており、参加者はコンセプトカーと一緒に記念撮影した動画をダウンロードして持ち帰ることができる。栗原氏は「今回、来場した方に自分だけの、特別感があるコンテンツを用意できないかと考えた。SNS上などでシェア・拡散され、話題になることも期待している」と話す。

Concept Car Virtual Stageでは、ステージ背面と床面のLEDディスプレイに動画を流し、そのLEDディスプレイをカメラで撮影する際に、カメラの位置に合わせて映像を変化させることで、平面的な動画を立体的に見せる技術を活用した。来場者はステージに上がり、選んだコンセプトカーと並んで記念撮影(動画)ができるため、あたかも実際に車が存在するように見える。
なお今回はコロナ禍の開催で、来場が難しい人向けにバーチャル体験ツアー「Innovation Walk(イノベーション・ウォーク)」が用意されている。会場内を移動するロボット視点で、実際のイベントのようすを見ることが可能だ。





![[セミナーレポート]伊豆大島、島ぐるみでMICE誘致へ動く ―東京観光財団](https://www.eventbiz.net/wp-content/uploads/2025/10/PA073837-218x150.jpg)


-218x150.jpg)