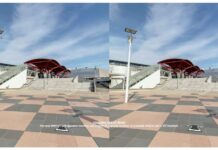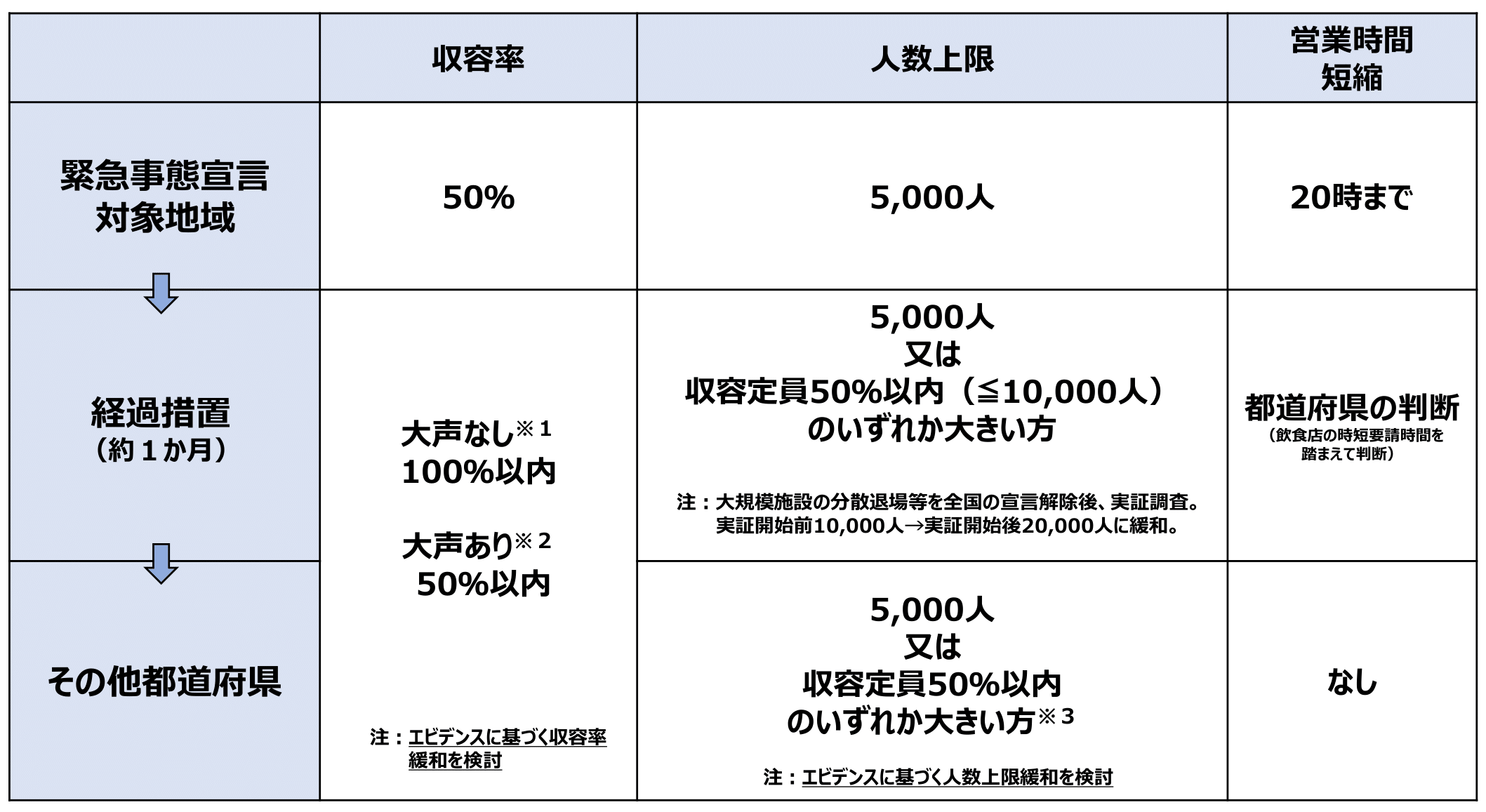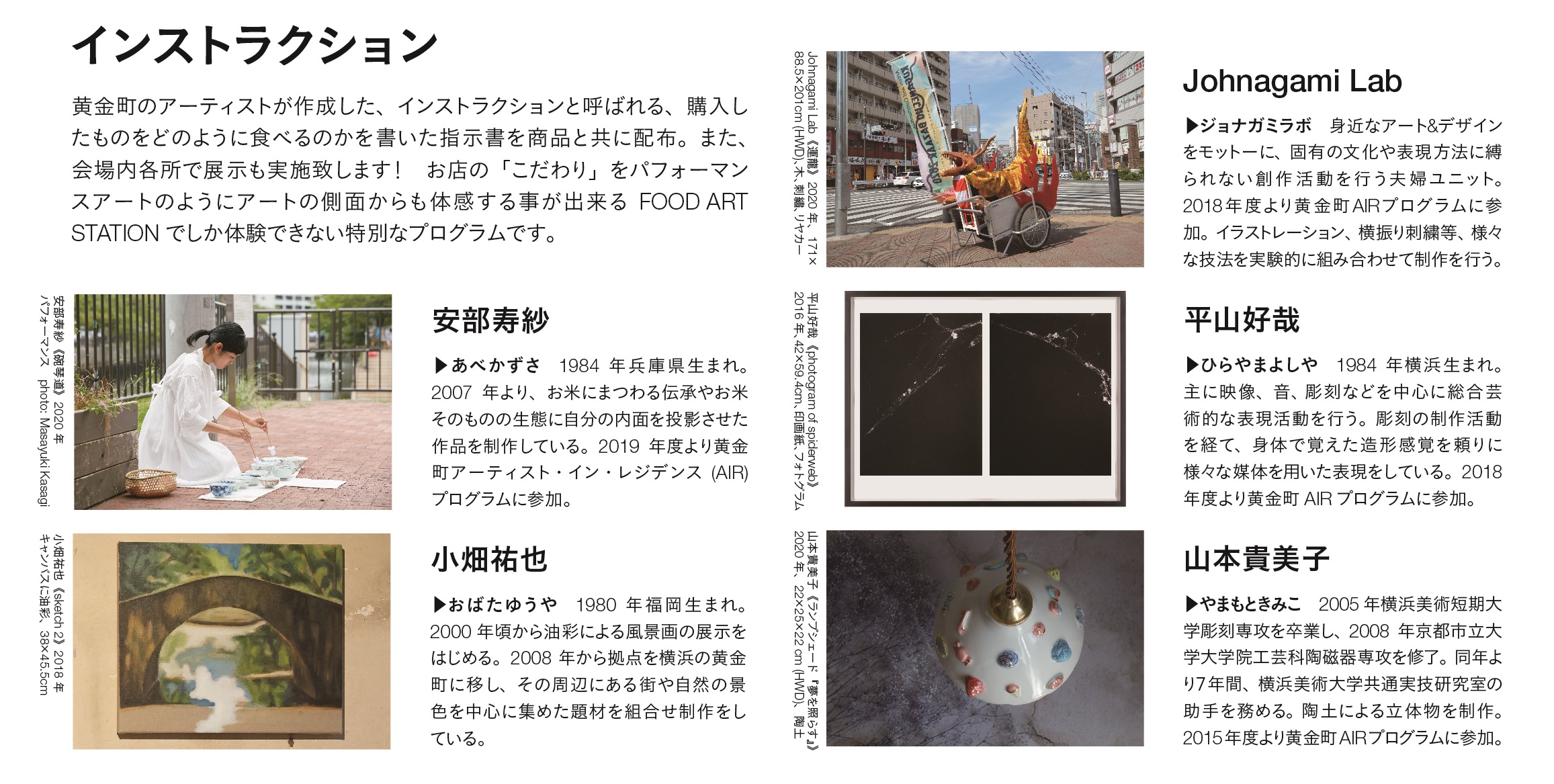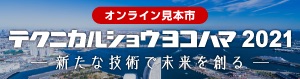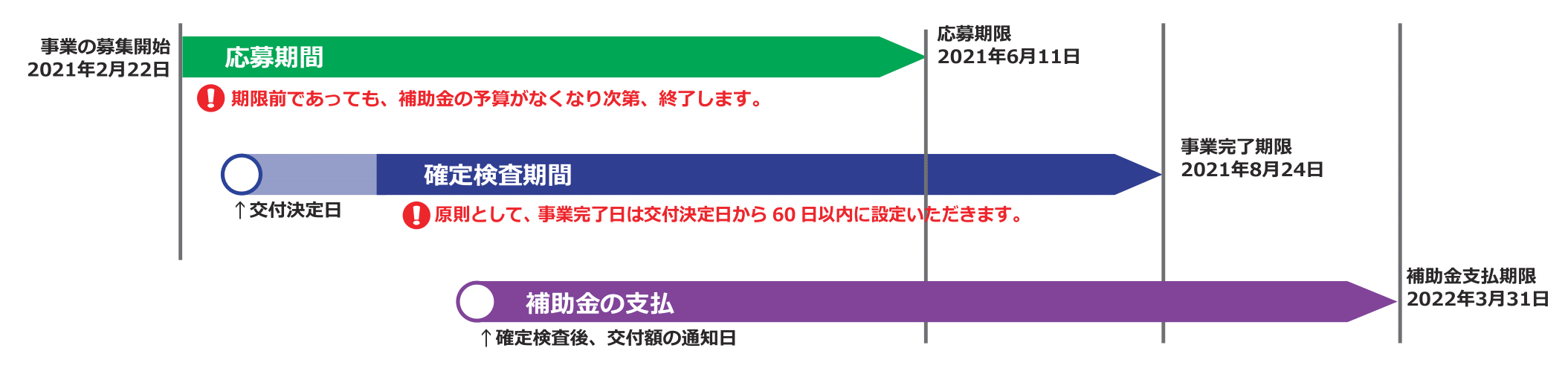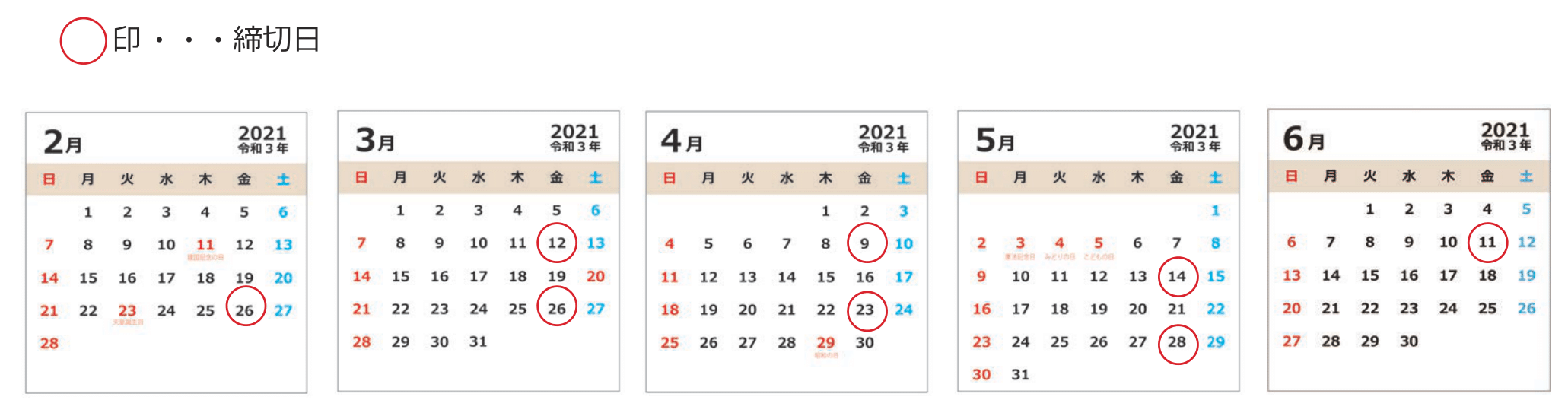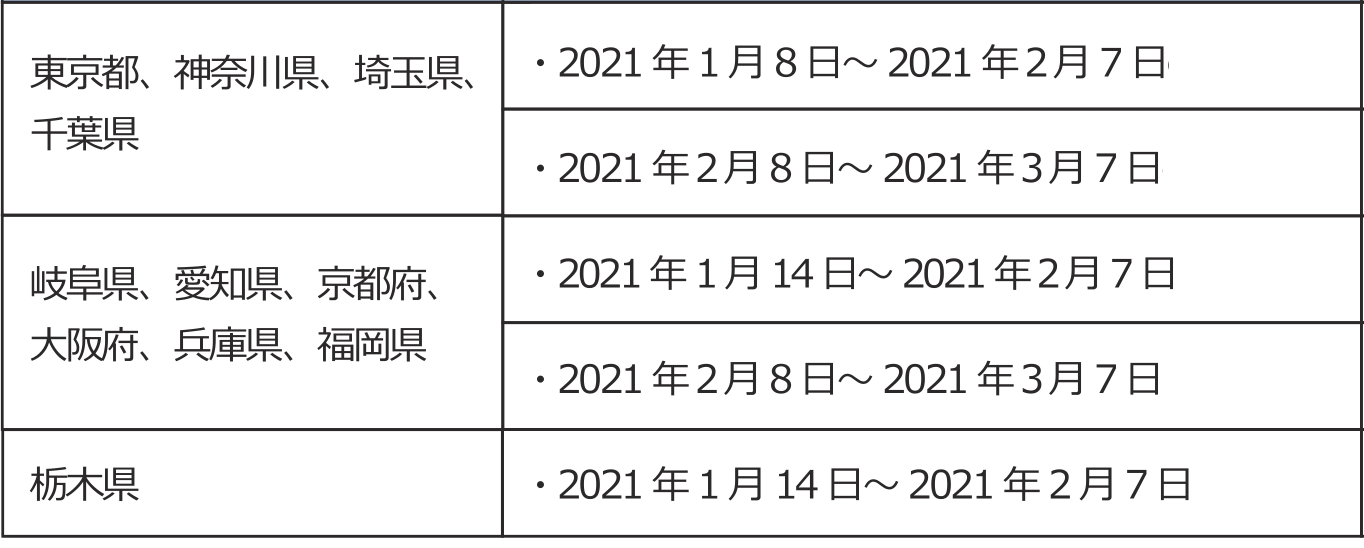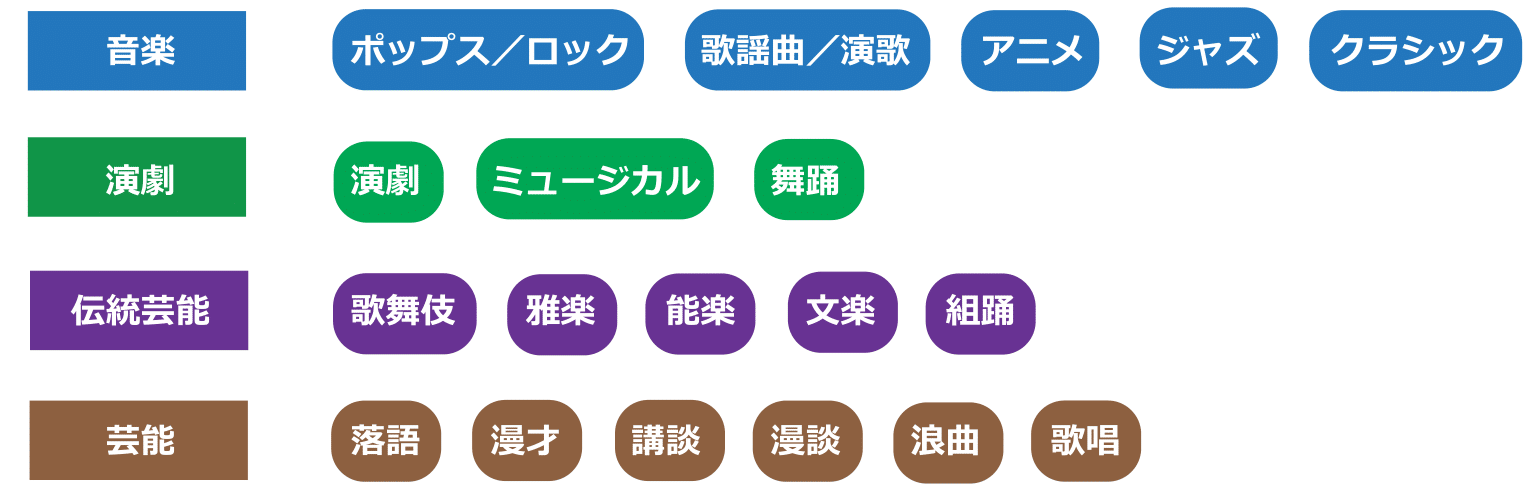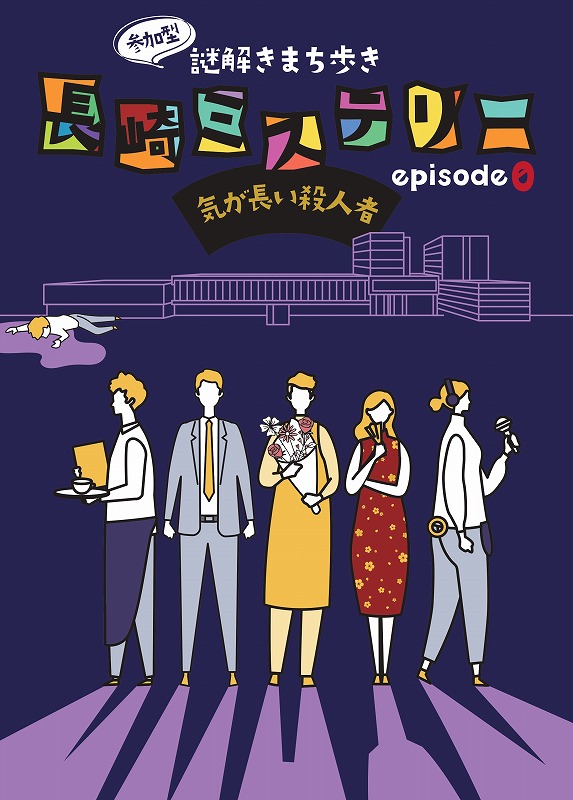2020年2月から続く新型コロナウイルスの感染拡大。二度目の緊急事態宣言により、現在もイベントは開催中止や延期を余儀なくされ、各企業は休業やテレワークといった対応を迫られている。しかし、電子化による業務効率化や新しいコミュニケーションの機会の創出など、新型コロナがもたらした変化は決して悪いものばかりではない。日本映像機材レンタル協会(JVRA)に所属する5人に、昨年からの今までの状況を振り返りながら、コロナ禍での対応や社内で起こった変化について語ってもらった。
▽登壇者
・菊地 利之 氏
ヒビノ/ヒビノビジュアルDiv. Visualオペレーション部 部長
・小山 良介 氏
シネ・フォーカス/総務部部長
・永田 巧 氏
光和/レンタル本部 第一営業部 部長
・鈴木 幸一 氏
光響社/取締役 事業本部長
・八谷 啓介 氏
シーエーブイ/イベント映像事業部 札幌事業所 次長
▽新型コロナがもたらした変革
コロナ禍により、社内でどのような変化が起こりましたか
リモートワークを余儀なくされて、ZoomやTeamsといったオンライン会議システムを日常的に使うようになったのが一番大きな変化だと思います。
ミーティングが気軽に行えるようになって、クライアントとの打ち合わせの機会が増えましたよね。もちろん顔を直接合わせるべき場合もありますが、やっぱり普段のちょっとしたやりとりには便利です。周りの会社を見てみると、全く出社しなくてもいいという会社と出社すべきだという会社で、意見が二分している印象です。もちろんクライアントとのやり取りでは、こうしたツールをすでに皆さんも活用していると思いますが、社内のスタッフ同士の打ち合わせでも会議ツールを使っていますか?
私たちもほぼリアルで打ち合わせを行っています。基本的に私の会社では準備から片付け・搬出まで1つのチームで進めており、荷物を積み込みながら仕事の打ち合わせしていることも多く、業務の一部だけをリモートに切り替えるのは難しいからです。
休業やテレワーク中、社員に対してどのような取り組みを行っていましたか
イベントが開催できない時期を利用し、新入社員に対して研修を行いました。例年、新入社員が入ってすぐに繁忙期に突入してしまうため、なかなか基礎から丁寧に仕事を教えるということは、正直できていませんでした。しかし今年は幸か不幸かコロナ禍によって時間ができ、LEDパネルを組むといった現場の基礎を学べる研修を行いました。すると、いざイベントが再開してみると、新入社員の現場での動きが格段に良くなりました。基礎が分かっていることで、現場でも効率よく立ち回ることができます。研修を経たことで実際の現場で上司とのコミュニケーションも円滑に進んでいたように思います。
休業になってから、改めて映像、電気について勉強し直している姿が見受けられました。いまさら聞けないことを含め。十年選手にもなると、業界や仕事の当たり前のことを知らなくても、なかなか素直に聞けないものです。
また、休業を始めて1~2カ月ほどでライブをオンラインで配信しようとする動きが生まれました。しかし「オンライン配信はリアルの代替」というイメージを払拭するような、配信ならではの良さを生かしたコンテンツを用意する必要がありました。特にXRなど先端技術による新しい付加価値の創出を期待しており、どういったコンテンツが作れるかを、社内で研究しています。大型ライブが中止になり時間ができたため、若い世代からアイデアを募り、デモンストレーションまでを行いました。
夏ごろからようやくイベント再開の兆しが見え、配信ライブに加えてリアルイベントでも制限下とはいえ観客を集めることができるようになり、若手が研修や休業時に勉強したことを実地で試せる良い機会になりました。私たちのようなイベント映像に関わってきた人間には「オンラインは儲からない」というのが通説ですが、例え配信だけの小さなイベントでも、若い世代の「会社に貢献している」という大きなモチベーションにつながりますね。やっぱり「何かしたい!」という気持ちは誰しもが持っているものです。
私たちも今後リモートが世間に普及していくことを見越して、自分たちがどこまで配信サービスに対応できるか、夏ごろから研究を始めました。
ただ、ふと考えたことがあって。新入社員はオンライン配信の仕事をやりたくて入社したのではないということです。今までのイベントの在り方を見て、リアルなイベントでの仕事をしたくて入社してきているわけですから。もちろん折り合いを自分でつけてもらうしかないんですが、できるだけやりたいことに近い仕事を用意したり、リアルにつながる点を示したり、大きな行き違いが生まれないようにすり合わせをしたつもりです。
自分は逆に現場に向かう若い社員を見て、「若い世代が頑張っているから自分ももっと頑張ろう」と自分のモチベーションをあげていました。
コロナ禍は、自分たちの仕事観を見直す時間や社内で価値観を共有する機会を創り出したかと思います。その中で、見えてきた課題はありますか
時代に沿って配信技術を習得していく中、今後配信サービスをどこまで充実させるべきか悩んでいます。イベントができるようになるまでのつなぎとして運営するのか、それとも本格的に企業の柱の事業にしていくべきなのか。
内政的な部分ではテレワークが浸透していくにつれて電子化の必要を感じ、出退勤の管理や経費精算の電子化を進めました。
昨年、イベント現場での仕事が再開しだしたころ、東京に営業所へ誰が出張するかで社内で問題になりました。若い社員の中では、東京に出張へ行きたくないという人も、気にせず業務を進めるという人もいました。ところが、東京に行ってもいいという人から「行きたくない人はその希望が認められるのに、リスクの高い場所で仕事をする僕たちに手当はないんですか?」という意見があり、社内で待遇を考えながら、はたと気が付いたことがあります。
例えコロナ禍だとしても、クライアントに来てほしいと言われたら私たちは応えるべきで、そうした心構えで今までも仕事と向き合ってきた。テレワークでできる仕事がないわけではありませんが、現場で動き回って初めて成立する仕事が大部分を占めていて、それが本来の私たちの仕事です。誰を行かせるかではなく、平等に今まで通り適材適所、行くべき人が現場に行く。ですから、状況に振り回されてはしまいますが、もう一度本当の自分の仕事は何か、やるべきことは何か、自分のやりたいことは何だったかということに、きちんと向き合ってほしい。若い世代に伝えながら自分自身にも改めて問いかけました。
根本的な部分に立ち返り、自分たちの仕事の必要性について考え直しました。リアルイベントと配信イベントだけで会社を運営していくのか、それともほかの生きる道を模索するべきなのか。事業のすそ野を広げることも視野に入れていました。実際に北海道には音響スタッフとしての仕事をしながら農家を兼業している人もいます。とはいえ今まで通りイベントでお客さんの喜ぶ顔をたくさん見たいですし、新事業には至らなかったんですけどね。
コロナによって、社員の仕事に対する思い入れや考え方が今まで以上にわかるようになりました。先導する立場にいる人たちは仕事に対する考え方について、どの社員も同じように真摯であってほしいと願っています。しかし現実には、社員一人一人が異なる考え方を持っていて、決して一律に同じ態度で接すること、成果を求めることが正しいとは限りません。今後は企業も、彼らの持つ多様性を認めながら歩んでいかなければならない時代だと思います。
▽コロナ時代を生き抜く
今後の展望はありますか。また若い世代にメッセージをお願いします
最初は仕方なくこなしていた配信の仕事が、今では会社の命綱になっています。今後はZoomやYoutube Liveのほかにも、さまざまなプラットフォームやツールを活用したコンテンツを率先して生み出していきながら、事業の新しいスタンダードも創り出していきたいです。
歴史を振り返ると何度も大きなターニングポイントがあり、そのたびに世の中が大きく変化しています。この動きにいち早く着いていくことができた人が先駆者になっていくのだと思います。暗く考えすぎずに。こんな状況だからこそ、これまで思いもつかなかった楽しいことや新しいアイデアが思い浮かぶかもしれません。
今まで高かった社内のシステムを変えるというハードルが新型コロナウイルスによって低くなっているため、これをきっかけに効率化を図っていきます。「電子化」という単語は、従前の方法に慣れている方にとってはかなり警戒されやすいものです。しかし、コロナを発端とした社会態様の変化は新しい方法を受け入れやすい面もあり、変革を一気呵成に進めるチャンスでもあります。新しい常識を作っていくのが自分たち自身だという自覚をもって、共に励んでいきましょう。
配信ライブは全くネガティブなものではないというのが、今のところの私の見解です。とあるアーティストのライブ配信では、3,600円のオンライン視聴チケットをおよそ18万人が購入したそうです。そして、チケットを購入した人の家族や恋人、友人など一緒にライブを視聴した人を含めると、約50万人が視聴したと推定されています。この結果からも、「ライブ配信イベント」というコンテンツが確立し、大きな価値があるということが分かりました。今後は生のライブと違って、ディスプレイの中で平面的であるという特徴を持ったこの新しいコンテンツで、どうやって観客の目を楽しませるかを工夫していく必要がある。この工夫こそが、今後のライブ配信イベントが発展するための重要な軸だと推測しています。
それでもやっぱり「生のライブ」を楽しめるようになる日が1日も早く来ることを願ってやみません。そして落ち込んでしまったリアルなライブを回復させていくのは、若い世代の社員だと思っています。紀元前、紀元後ではないけれど、ビフォーコロナ、そしてアフターコロナという時代の境目だと考えて、新しい映像表現にトライしてほしいと思います。
引き続きしばらくはオンライン会議システムを使ったセミナーやライブ配信が日々の業務の中心になっていくと思いますが、小さなイベントでもコツコツと仕事をこなしているということは、誰かの役に立てているということです。
世間のニーズに沿って、あらゆる技術が進化していきます。映像の世界もフィルムからデジタルへ急速に変化を遂げました。今まで以上に動きの激しい時代ですが、常に半歩先を見据えながら、映像の世界のスピードと大波を乗りこなしてほしいです。特に目まぐるしく入ってくる新技術を素早く吸収できる若い世代にとっては、先輩を出し抜けるいいチャンスですよ。それを楽しみにして努力を惜しまずに。
ありがとうございました
☞前回座談会はコチラ!
「子どもも会社も育てる! 映像業界で働くパワフルなママたち」