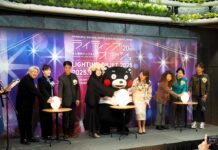64年東京五輪のデザインが集結
2月13日、東京近代美術館で「東京オリンピック1964デザインプロジェクト」が開幕。1964年に開催された東京オリンピックにまつわる作品群を展示している。
東京オリンピックはスポーツの祭典にとどまらず、戦後のデザイナーが総力を挙げて取り組んだ一大デザインプロジェクトでもあった。デザイン評論家の勝見勝による指揮のもと、シンボルマークとポスターを亀倉雄策、入場券および表彰状を原弘、識章バッジを河野鷹思、聖火リレーのトーチを柳宗理が担当。田中一光をはじめとする当時の若手デザイナーたちが、施設案内のためのピクトグラムや、プログラムや会場案内図などの制作に組織的に取り組んだという。
4月21日(13:00~17:00)には公開シンポジウム「社会システムの中のオリンピックと<デザイン>」が開催される。出席者は東京藝術大学の佐藤道信氏、首都大学東京の長田謙一氏、パーソンズ美術大学のジリー・トラガヌ氏、東京工科大学の暮沢剛巳氏、ニッセイ基礎研究所の吉本光広氏、同館主任研究員の木田拓也氏。
また、5月12日(14:00~16:00)には座談会「東京オリンピックのデザイン証言者」が開催され、勝井三雄氏、小西啓介氏、道吉剛氏が登壇する。
2020年のオリンピック招致にむけた機運が高まるいま、あらためて1964年の東京オリンピックを振り返り、一連のデザインワークの全体像を追跡する。
開催期間:2月13日~5月26日
開場時間:10:00~17:00 ※金曜日は10:00?20:00、入館は閉館30分前まで。
観覧料は一般420円、大学生130円、高校生以下および65歳以上は無料。
詳細は東京国立近代美術館のウェブサイトを参照すること。
同展のようすは見本市展示会通信春季特集号の「オリンピック招致に向けて」でもお伝えする予定。