
アメリカ館
占部 世間でも話題になっている人気のパビリオンですね。視察の日は平日でしたが、私は2時間半並んで、なんとか入れました。木村さんもどうにか入場されたんですよね。
木村 はい。それだけ体験も素晴らしく、アメリカのパワーを見せつけられました。宇宙船をイメージした空間で、メインのエリアは高さのあるLED ディスプレイと鏡で囲まれていました。スモークや床の振動、音も演出に取り入れられ、大迫力のコンテンツ。ディスプレイのつなぎ目もきれいで臨場感がありました。(写真④)
占部 天井にもLED で映像が流れていました。ロケットに乗って宇宙ステーションに行くというストーリーでしたが、床振動はかなり揺れましたね。振動があるとストーリーに没入しやすい気がします。こうした床振動を含めた技術のことをなんというんでしたっけ?
木村 ハプティクスですね。人間の触覚に振動、動き、力などの感覚を与える技術のことです。イベントだと振動や風を感じさせる体験がこれにあたります。
〇サウジアラビア館
占部 サウジアラビア館はお2人が視察して、2人とも良かったと言っていた場所ですね。
但木 本当に良かったですよ。運よく入場が難しい夜のショーにも入場できました。サウジアラビアに伝わる神話と音楽を体感できます。各国パビリオンの高さ制限がおそらく12m程で、ギリギリくらいの高さがあったと思います。(写真⑤)高さのある映像を流すだけでなく、立体音響を使用し、さらにアーティストによる歌とチェロの生演奏も組み合わせていました。
使っている演出手法は非常にシンプルながら、世界観や異文化、迫力を感じられる非常に優れた没入体験でした。

木村 加えて面白いポイントが、パビリオンの建築自体にも風が通る設計がされていたところです。中に入ったときに、ふっ、と風がくるというか、涼しさがずっと続くんです。映像も実写を使ったシーンが多く、CG だけの映像と違って飽きさせないものに仕上がっていました。

〇中国館
木村 まず中国館は紙が開発される以前、古代中国で記録に使われていた竹の巻物「竹簡」をモチーフにした建物が印象的でした。館内もモチーフが引き継がれていて、LEDディスプレイを使って壁の竹の上に文字が映し出されるようになっていました。さらにその文字は床までつながっているのですが、床の映像はプロジェクターで投影していました。
占部 プロジェクター、数えてみました? 相当な数でしたよね。途中で数えるのを諦めるくらいの台数が吊られていて、私も圧倒されました。円形の巨大なLED ディスプレイもインパクトがありましたよね。古代中国の暦「二十四節気」や最新のテクノロジー紹介していました。7,8mくらいはあったかな。しかもわざわざ傾けて置いていて。(写真⑥)
木村 とんでもない大きさの円形でしたよね。
占部 中国館ではお手本になりそうな透過ディスプレイの使い方もありました。展示品の前にショーウィンドウのように透過ディスプレイを置いて、一部をタッチして操作できるようにしていました。
木村 古代の冠や宝飾品など、実際には触れられない展示物の3D データを、タッチで自由に動かして裏側も見られます。今回の展示では歴史や解説も閲覧できるようにしていました。今後博物館や資料館でも、こうした透過ディスプレイの導入が増えていくのではないでしょうか。
〇住友館
但木 グループで1つランタンを持ち、暗い森のような空間を散策します。このランタンが「赤い扉を探して」など喋って光りながら、案内役を務めてくれます。特定のマークがついている切り株や枝にランタンを置くと演出映像が流れ、テーマパークのようでした。車いすでも進めるようになっていたり、風が吹いて行くべき道に誘導されたり、体験が丁寧に設計されていました。
占部 ほかにも気になる演出があったそうですね。
但木 ホログラムLED による演出です。虫の映像を投影し、どうしても発生してしまう機材のファンの音を、虫の羽音として演出していました※1。館内には10台ほど置いてあったと思います。ホログラムは使い所が難しく、展示会でも頭上の高い位置に置くことが多いのですが、演出を工夫すれば目線の高さの展示でも活用できるんだなと。
※1…ホログラムLED はプロペラ上のアームに取り付けられたLED を高速回転させることで空中に映像を描く仕組み。そのため構造上、回転時に風切り音が発生する





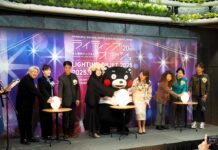


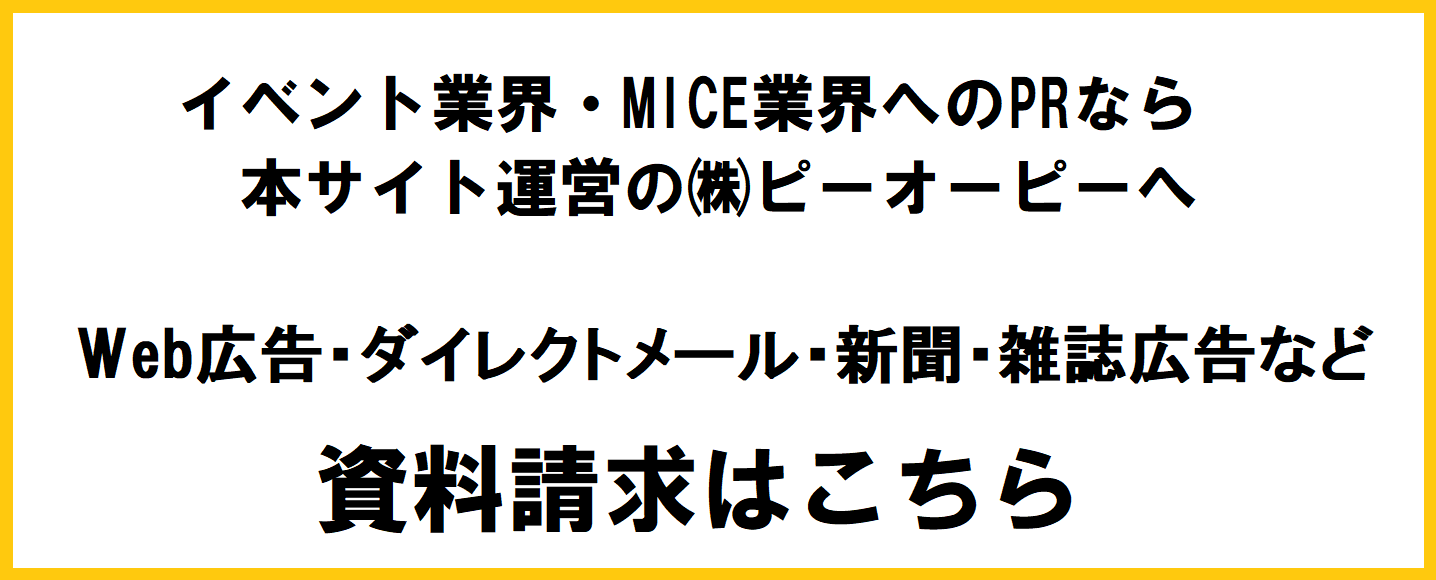

![[講演会レポート]展示会の集客力を高める工夫を解説 – 第15回 夢メッセみやぎ講演会](https://www.eventbiz.net/wp-content/uploads/2025/02/P2181115-218x150.jpg)



