
私どもカマタニは大正8年(1919年)創業、官公庁の制服や各種企業の事務服、作業服、そしてアミューズメント施設のスタッフユニフォームなどを企画、製造、販売、レンタルを行なっている会社です。MICE産業では、昭和60年(1988年)よりイベント用の短期レンタルユニフォームに注目し事業を展開してまいりました。3日・6日・10日間にて期間を設定し、展示会の開催期間のみユニフォームをレンタルしていただいております。ほぼ全てが当社オリジナルデザインで、企業のコーポレートカラーや商品イメージ、またブース装飾に合ったユニフォームを一着より必要な枚数のみご利用いただくことで、無駄な経費をかけずにイベントをより効果的に演出していただいております。
<ユニフォームがもたらすイメージ効果>
展示会や、各イベントではイメージ作りが大きな役割を果たします。今の時代、商品の過剰包装は敬遠されていますが、同じ商品でも桐の箱に入っていたり、パッケージや包装の仕方によって随分と値打ちが違って見えることは否めない事実だと思います。われわれは企画制作会社とタッグを組んで、展示会、諸々のイベントをより一層盛り上げるためのイメージ作りを考え、特に衣装の分野でお手伝いをさせていただいています。4年後に開催される東京オリンピックでも、さまざまなユニフォームが必要になってくると思われます。弊社のレンタルユニフォーム「Bendy」では、展示会以外にもさまざまなシーンでご利用いただけるユニフォームを今後も企画・製作してまいります。
<ユニフォームの歴史>
ミニスカートブーム到来~1960年代~
ユニフォームの歴史的な流れを見ますと、1960年代までは事務服においても、作業性が中心で、汚れが目立たない服、また自分の服が汚れないようにすることが主な目的で、上っ張りやスモックタイプが大半でした。1967年ミニスカートの女王「ツィッギー」の来日によりミニスカートブームが興り、事務服の世界にも波及していきました。
万博をきっかけに高いファッション性に~1970年代~
そして1970年の大阪万博(日本万国博覧会)の受付や各パビリオンのコンパニオンのユニフォームを契機にして、一般のファッションも多様化するようになり、ユニフォームの世界もますますファッション性が要求されるようになりました。大阪万博ではワンピース型のユニフォームが多く採用されていたので、それ以降ユニフォームにもワンピースや、動きを良くする為にノースリーブにしたジャンバースカート等が主流になって来ました。
CIブーム、バブルの到来~1980年代~
1980年代に入るとCIブームが興り、多くの会社で企業理念、事業内容、社会的責任等々を改めて問い直し、自らの存在価値を企業の内外で共有するために、企業イメージを確立し、価値観、行動規範、ロゴマーク、企業カラー等々、を新たにして企業の個性を表現していきました。ユニフォームもロゴマークや企業カラー同様、社の内外に見えるメディアとして、また社員連帯感の醸成や、働く意識の向上、自社へのプライドや愛着心の高まりを促すものとしての大きな役割を担いました。1980年代後半に入るとバブル経済が盛んになり、ユニフォームもDCブランドがもてはやされ、どんどん多様化、高級化していきました。この頃お客さまからは「高くてもいいから、もっと良いものを持ってきてくれ」と言うお声が頻繁に聞かれるようになりました。

迫られるコスト減~1990年以降~
1990年代前半にバブル経済は崩壊し、今度は一転してコストの見直しが行なわれ、大幅に予算が削減され、また制服自由化の名の元にユニフォームを廃止にされる企業も多く現れて来ました。近年は逆に、ユニフォームの価値や効用が見直され、復活をされる企業も増えて来ております。

環境志向や省エネ志向に~2000年代~
2000年に入りますと、環境が叫ばれ、ISO14000番台を取得される企業が多くなり、ユニフォームもリサイクル素材のものや、リサイクルが可能な商品が求められるようになりました。2008年にはリーマンショックに見舞われ、デフレ経済の中、景気の低迷と共に事務服分野もモノトーンのものが多く出回るようになってきました。引き続き2011年東日本大震災からしばらくの間は、全てにおいて自粛ムードと、エネルギー不足による省エネの機運で、クールビズ対応とカジュアル化が進んできています。
<MICE業界を通して>
MICE業界でも全体的に今まで説明してきた流れと同じ傾向があり、また、景気が悪くなれば白や黒のユニフォームが増えてきて、景気が良くなれば綺麗な色のものが増えてくる傾向も、われわれの業界の流れと変わりがないように見受けます 。これからの時代、商業・工業・農業・IT・金融等々のあらゆる分野で、輸出輸入、人材など、ますますグローバル化し活発化していく中で、MICE業界はますます重要な位置づけとなって来るでしょう。その中で業界に関わる各企業が、自分の位置づけや役割を明確に打ち出すと共に、業界そのものの有り方をも考えながら、行動していくことこそ大切だと考えます。
(株式会社カマタニ 代表取締役 鎌谷 正弘 氏より寄稿)






-218x150.jpg)










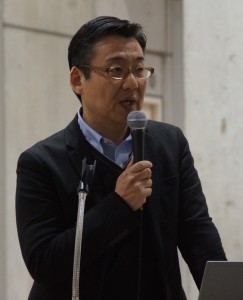








 中野 信男 氏(中野科学社長)
中野 信男 氏(中野科学社長) 小林 成年 氏(名古屋眼鏡社長/日本眼鏡関連団体協議会副会長)
小林 成年 氏(名古屋眼鏡社長/日本眼鏡関連団体協議会副会長)