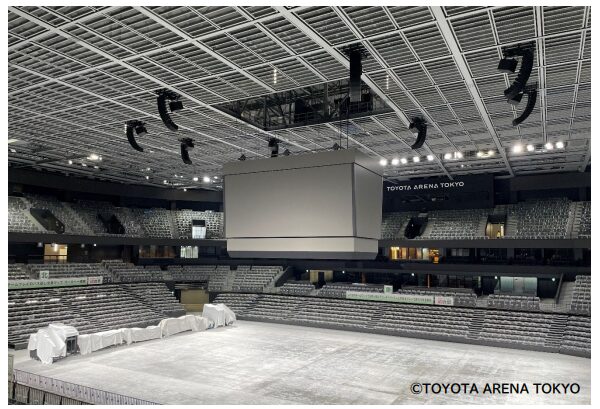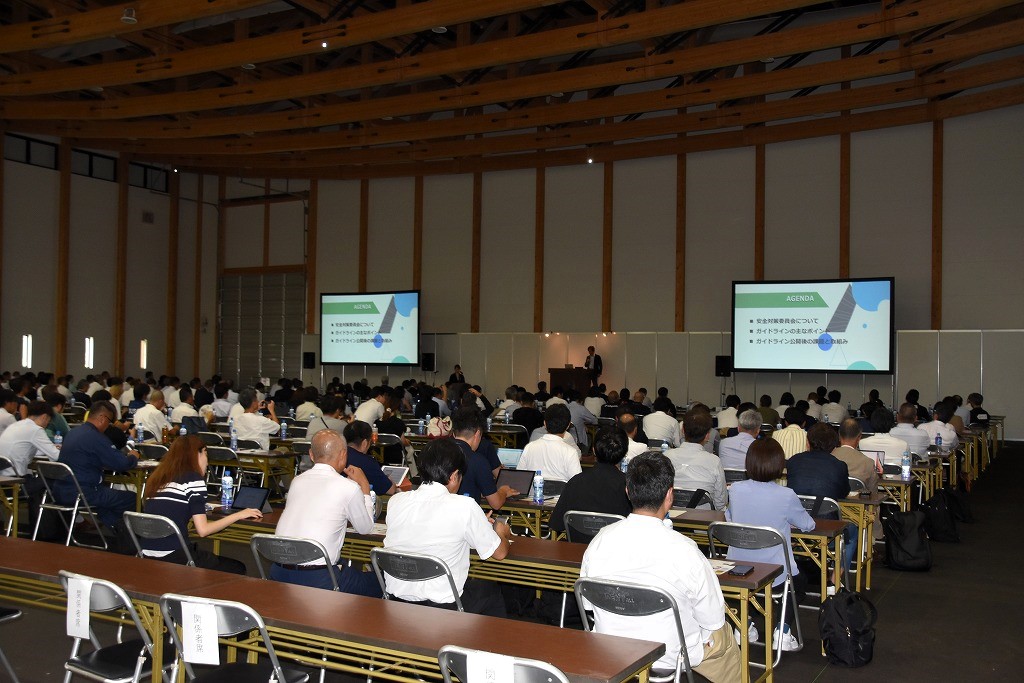2025年の大阪・関西万博では、さまざまな国や企業による個性的なパビリオンが建設されている。参加国が自ら設計・建設する「タイプ A」パビリオンは47カ国42棟。その中で最初に完成したのがアイルランドパビリオンで、イベントの企画制作や運営などを手掛ける TSP 太陽が施工を担った。今回、担当者である森哲二氏に、海外設計による意匠を日本で具体化したプロセスについて聞いた。
(EventBiz vol.39 特集「開幕!大阪・関西万博」より転載)

TSP 太陽
事業統括本部 プロデュース事業部
2025 万博 PJ /課長
森 哲二 氏
デザインを“翻訳”する

─外観が印象的なアイルランドパビリオンですが、どのような経緯で実現したのでしょうか
パビリオンの基本的なデザインは、アイルランドの公共事業局(Office of Public Works / OPW)の設計チームが担当しました。外観の意匠やコンセプトはアイルランド側の意向を尊重したものです。
当社の役割は、そのデザインを日本の建築基準法や建材の実情に合わせて実現していくことです。例えば「この素材は日本では使用できない」「この工法は法規制に抵触する可能性がある」といった点を洗い出しながら、現実的な代替案を提示しました。
中でも象徴的なデザインである「トリスケル(三つの円が重なる形)」は、表現の核となる重要な要素でした。しかしながら、丸みを帯びた構造であるため、直線を基本とする日本の鉄骨施工とは発想が異なります。曲線を多用する設計はコストがかかるためです。実際には、直線的な鉄骨部材をどのように組み合わせて曲面を表現するかという点に技術と工夫を注ぎました。
また、外壁に使用している木製ルーバーはアイルランド産の木材を使っています。まだ現物が製材されていない段階から、ピッチや奥行きによる見え方を事前に確認する必要がありました。日本でモックアップを製作しながら、アイルランド側と細かい調整を重ねました。こだわりに丁寧に向き合い、しっかりとかたちにできたと思っています。

国境を越えたチームワーク
─海外プロジェクトということで、言語や文化の違いで苦労された点もあったのでは
ありましたね。打ち合わせは基本的にすべて英語で行われたため、毎回の会議に相応の準備が必要だったことはもちろんですが、時差の関係もあって。日本時間の夕方6時から夜9時までが打ち合わせの時間帯になることが多く、通訳担当の負担も大きかったです。製作図面も英語に翻訳して提出する必要があったため、通常以上の工数がかかりました。
一方で、アイルランドの関係者の方々は終始フレンドリーで、文化や言葉の違いを超えてスムーズなやりとりができました。チームワークの良さを強く実感した仕事でもありましたね。
─夢洲という特殊な会場での施工について難しかった点はありますか
夢洲は埋立地ゆえに地盤があまり強くありません。そのため、建物によっては杭打ちが必要になるケースがありますが、アイルランドパビリオンは比較的軽量な構造だったため、できるだけ建物の重量を抑えることが求められました。博覧会協会から推奨された工法の一つである「浮き基礎」*はアイルランド側では馴染みがなく、実施にあたり丁寧な説明が必要でした。
*浮き基礎…建物の重さと同等の土を事前に取り除くことで、地盤への負荷を抑える基礎工法。

─「タイプA」パビリオンの中でアイルランドが完成第1号でした。長期間にわたるプロジェクトでしたが、振り返ってみていかがでしたか
施工期間は2024年1月の着工から2025年2月末の引き渡しまで、1年以上にわたりましたが、小さな事故さえも一切なく完了できたことは大きな成果でした。
実は今回、設計を担当していたOPW の担当者は、建設期間中に一度も現地を訪れることができませんでした。そこで、現場にライブカメラを設置し、進捗状況を3D データと合わせてオンラインで共有する仕組みを整えました。実際に、OPWの方が初めて現地を訪れたときに「自分たちが描いた通りの建物ができている」ととても喜んでくださったのが印象的でした。
文化を体感する空間
─来場者には、どのような点に注目してほしいですか
今回の展示は、他国のパビリオンのようなデジタル技術で驚かせる演出ではなく、より五感で味わうような空間体験が特徴です。
大きなホールではアイルランドの雄大な自然風景が大画面に映し出され、現地の音楽と組み合わせることで、非常に落ち着いた雰囲気の中で文化を感じられる構成になっています。ぜひゆっくりと過ごしていただきたいです。
屋外には、金色の大きなリング状のモニュメントが設置されています。これはアイルランドの著名なアーティストであるジョセフ・ウォルシュ氏による作品で、現地から日本に輸送されてきたものです。その周囲には、季節ごとに表情が変わる植栽が施されています。アイルランドの風景に調和する樹木が選ばれており、時間の経過とともに空間の雰囲気も少しずつ変化していきます。
また、日本でいう「手水鉢(ちょうずばち)」のような石が配置されているのですが、これもアイルランドから持ち込まれたもの。水が流れる中で石が数百年もかけて自然に削られたもので、非常に貴重な展示物です。会期終了後にはアイルランドに戻される予定です。
今回、アイルランドから来ている学生や留学経験のある日本人スタッフも運営に携わっています。彼らもとてもフレンドリーで、来場された方にも、そのあたたかい雰囲気を感じ取っていただければ嬉しいです。